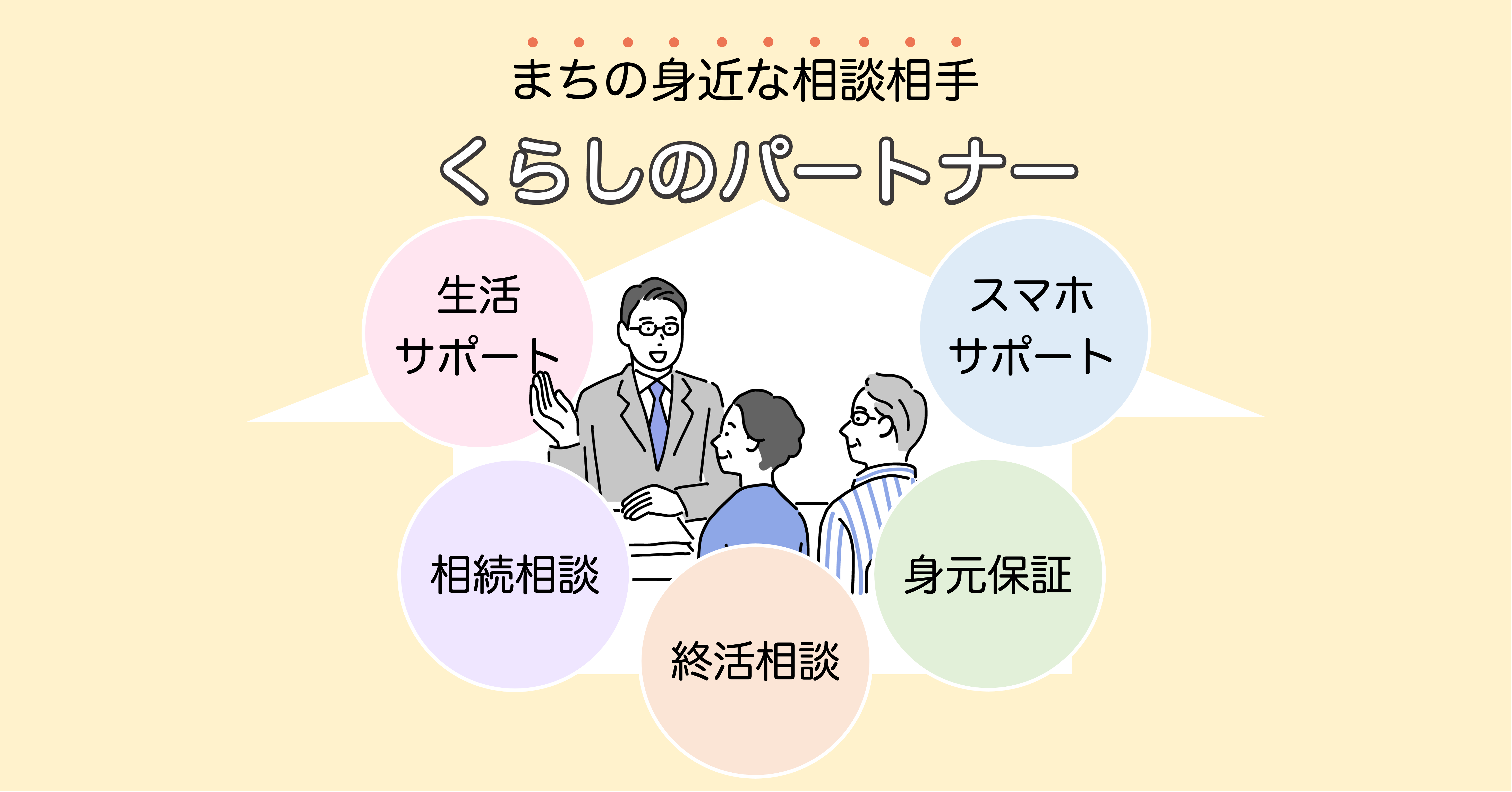高齢者が感染しやすい感染症のうち、誤嚥性肺炎があります。誤嚥性肺炎は最悪の場合には死に至ることもあり、高齢者本人は勿論のこと、介護者も気を付けてケアを行わなければなりません。
今回は、まず誤嚥性肺炎について解説した上で、感染しないようにするには、どのようにすれば良いか詳しく説明していきます。
そもそも誤嚥性肺炎とはなにか

食べ物を食べた時、通常は喉を通り食道を通過し胃に辿り着きます。しかし、高齢になると食べ物が食道に行かず、肺の方に向かって行くことがあります。
これは、喉にある『弁』の機能が衰えてしまい、食べ物を胃の方に誘導できなくなってしまうということなのです。
食べ物が肺に行ってしまうと、そこで炎症を起こしてしまい誤嚥性肺炎になってしまうのです。
誤嚥性肺炎の症状について
若い人であれば、咳や発熱、それに膿のような痰が出ることがあります。しかし、高齢者の場合にはこのような症状が出ずに、知らず知らずのうちに状態が悪化してしまうことも珍しいありません。
よって、介護者は常に高齢者を観察し、活気がない、ボーっとしている、食欲がないというようなことがあれば、すぐに病院を受診するなどの対応が必要になってきます。
誤嚥性肺炎と診断されたら
病院を受診して誤嚥性肺炎と診断されたら、すぐに治療が開始されます。
医師の判断で軽度であると判断されれば、在宅で治療を行える場合もあり、抗生剤などの点滴が施行されます。
中度から重度であると判断された場合には入院をして治療を行うケースが多いです。在宅で治療を受けるのとは違い、24時間体制で看護が行われ、手厚くケアが行われるでしょう。
誤嚥性肺炎はこうやって予防しよう!

まずはとにかく誤嚥性肺炎にならないようにすることを考えなければなりません。
肺に唾液や食べ物に混じった細菌が行かないようにするためには、とにかく口にの中を清潔にさせておくことが重要になってきます。
口腔ケアは予防の基本!

基本は歯ブラシでしっかりブラッシングし、食物残渣物を除去していきます。義歯がある人は取り出してしっかり残渣物を除去し、口腔内もうがい薬で清潔に保つようにしましょう。
経管栄養者も口腔ケアは必要?
口から食事をしない、経管栄養者にも口腔ケアは必要になってきます。
前述した通り、誤嚥性肺炎の原因は食べ物だけではなく、唾液や痰などが肺に侵入しても発症するのです。
口の中が不潔だと、唾液や痰も不潔になりやすく誤嚥性肺炎のリスクは高くなるので、しっかりケアするようにしましょう。
口腔ケアの用具
口腔ケアの用具は歯ブラシだけではありません。義歯がない人、うがいが出来ない人などはコットンタオルやスポンジブラシを使って口腔ケアを行います。
コットンタオルは使い切りの商品で、ティッシュペーパーがコットンで出来ているようなイメージです。ビニール手袋をしてから指にコットンタオルを巻きつけて、歯や舌の汚れを除去していきます。
スポンジブラシは、歯ブラシのブラシの部分がスポンジになっており、水に浸してから口に入れて汚れを除去していきます。歯がない人に口腔内全体の汚れを除去する際に利用すると便利な商品です。
痰が絡みやすい高齢者は要注意
喉の奥からゴロゴロという音がして、痰が絡みやすい高齢者がいます。非常に粘りのある痰であれば、それがきっかけとなり窒息してしまうこともありますが、誤嚥性肺炎の原因になることもあるのです。
寝たきり高齢者になると痰を自分で外に出すことができず、自然にその痰が肺の方に流れ込んで行き、誤嚥性肺炎を引き起こすことも珍しくありません。
在宅介護であれば、訪問介護などを利用して看護師による吸引(痰の除去)を受けるようにして、口腔内を清潔にしていきましょう。
吸引をする器械は介護保険レンタルの対象商品ですので、気になる方は担当のケアマネジャーに相談するとよいでしょう。
口腔ケアで注意すること
高齢者の口腔ケアは難しいと感じることがあります。自身で歯磨きなどができる場合はいいのですが、介護者がケアを行う場合がいくつか注意することがります。
認知症などで、口腔ケアの必要性を理解できず、口を開けてもらえないこともあります。そのような時に、無理やり口の中に歯ブラシやスポンジブラシを入れると口腔内の粘膜を傷つけて、食欲不振などに繋がることもあります。
また、コットンタオルを指に巻きつけてケアを行う場合、指を噛まれてしまい怪我をすることもあるのです。
口腔ケアはとても大切ですが、難しいと感じたら歯科医師に相談するようにしましょう。
嚥下運動(体操)にも挑戦
嚥下(呑み込み)をスムーズに行うようにするために、嚥下運動に挑戦してみましょう。
ひとりでなく大勢でやってみる
高齢者がひとりで嚥下運動をするよりも、家族みんなでする方が継続して実施できるでしょう。
音楽を流したり、会話をしたりと、リラックスした雰囲気で楽しんで実施するのがポイントです。
嚥下運動の具体的なやり方
口を大きく開けたり、閉じたりすぼめたりします。例えば、「あ・い・う・え・お」「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ」と発音しながら、口の動きを意識してみるといいでしょう。
また、首周りの筋肉をほぐすために、可能な範囲で肩や首を回すようにします。
唾液腺をマッサージすることも大切です。首と顎の間に唾液腺があります。外から軽く押してみると唾液が出るのが分かります。
唾液が分泌されることにより、口腔内が潤いのある元気な口になり、咀嚼(噛む)をスムーズに行えるようになります。
嚥下運動を行うタイミングは、食事を食べる直前が理想です。