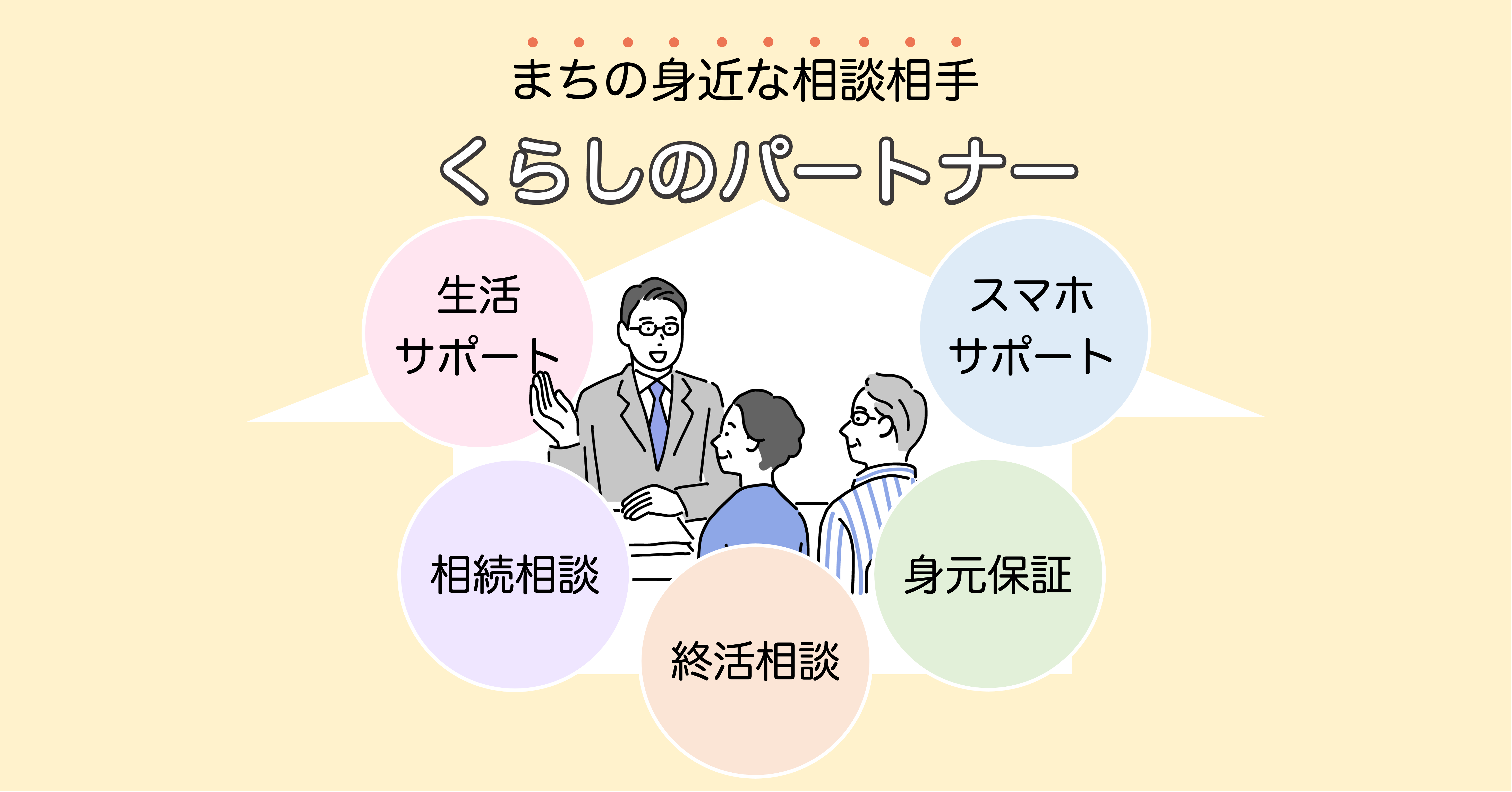大きな病気をして長期間入院したり、けがでギブスをはめて動かさずにいて、「体が思うように動かなくなった」という経験はありませんか?
これは廃用症候群(はいようしょうこうぐん)という立派な病気です。
高齢者の場合、何らかの原因で寝たきりの状態が続いてしまうと、廃用症候群を発症しやすく、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。
この記事では廃用症候群に関する基礎知識をご紹介します。
廃用症候群の症状や予防法、対策などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
廃用症候群とは

廃用症候群とはどのような症状の病気なのでしょうか?
廃用症候群の特徴や原因について、わかりやすく説明していきます。
廃用症候群の定義
厚生労働省は、廃用症候群を【生活不活発病】と位置づけ、
「動かない」(生活が不活発な)状態が続くことにより、心身の機能が低下して、「動けなくなる」こと
と定義しています。
高齢者特有の病気ではなく、状況によっては若年者に起こることもあります。
廃用症候群の特徴
高齢者において、廃用症候群は急速に進むという特徴があります。
1週間入院などで寝たままの状態になると、15%近い筋力の低下につながってしまうといわれています。
また廃用症候群を発症したことにより、認知症が進行してしまうという傾向も見られるので注意が必要です。
廃用症候群の原因
廃用症候群の原因は、過度の安静による心身の活動性の低下です。
安静にしなくてはいけない状況=ほとんどの疾患が原因として当てはまります。
代表的な疾患は
- 骨折
- 肺炎
- 認知症
- うつ病
- 感染症
- パーキンソン病
など、高齢者特有の疾患が挙げられます。
廃用症候群の症状を知る

廃用症候群になってしまった場合、どのような症状が現れるのでしょうか。
症状は多岐にわたるため、各分野に分けてご紹介します。
運動器の症状
運動器の症状として現れるのは、以下の症状です。
- 筋力の低下
- 怪我をしやすくなる
- 骨折しやすくなる
- 関節の拘縮
- 可動域の低下
運動器の症状は即寝たきりにつながってしまう可能性が高いため、廃用症候群も進行してしまう恐れがあります。
呼吸器・循環器の症状
廃用症候群は呼吸器・循環器にもさまざまな症状を引き起こします。
- 誤嚥性肺炎
- 心機能の低下
- 起立性低血圧
- 血栓塞栓症
呼吸器・循環器の症状は、命に係わる重大な症状が多いため、注意が必要です。
自律神経・精神の症状
廃用症候群は自律神経や精神状態にも悪影響を及ぼします。
- うつ状態
- せん妄
- 見当識障害
精神的な機能が低下することで、認知症の進行を早めてしまうケースも多く見受けられます。
褥瘡(床ずれ)に注意
褥瘡(じょくそう)とは、寝たきりの状態などがきっかけとなり、皮膚の血流が滞ることで起きる皮膚の病変です。
褥瘡は圧迫を受けやすい臀部(お尻)や腰骨の周囲、踵(かかと)、肘(ひじ)などに生じ、皮膚の赤み・ただれがみられます。
廃用症候群で注意しなければいけないのは、この褥瘡です。
褥瘡が悪化すると潰瘍(かいよう)や細菌感染を起こし、重症化してしまうこともあるので、体圧の管理を行うことが重要になります。
廃用症候群の予防と対策

さまざまな症状を引き起こしてしまう廃用症候群ですが、どのような方法を取ることで予防や対策に繋がるのでしょうか。
具体的な予防・対策方法を3つご紹介します。
寝たきりにしない
廃用症候群の予防でもっとも重要なことは、寝たきりにしないことです。
- ベッド上でも寝たきりにせず座る時間を増やす
- 着替え・排泄・食事など身の回りのことをできるだけ行う
- 関節痛などの痛みがある場合は医師に相談し薬物治療を行ってもらう
- 体位変換をきちんと管理して行う
など、動ける範囲で少しでも体を動かすことが一番の予防に繋がります。
脳梗塞などで麻痺が残っている場合でも、健側を動かすだけでかまいません。
痛みが原因で動くのが億劫になっているケースでは、薬物療法を行うことで動くことが怖くなくなります。
寝たきりの方の場合は、定期的に体位変換を行いましょう。
体圧を分散させることが重要なポイントです。
リハビリを行う
医師の指導の下、リハビリを行うことも有効な予防法です。
注意したいのは専門家以外の方が無理にリハビリを行うこと。
骨折等のトラブルを起こしてしまうので、必ず専門家に依頼して実施してもらいましょう。
在宅で介護を行っている場合でも、訪問リハビリを実施している事業者や通所施設も多くあります。
リハビリを利用することで、家族以外の人と接することも良い刺激になります。
バランスの良い食事を摂る
バランスの良い食事を摂ることも疎かにしてはいけません。
低栄養状態が廃用症候群を進行させてしまうこともあります。
肉類・大豆類・乳製品などのタンパク質をしっかり摂取し、栄養バランスの整った食事を心がけてください。
体を動かすために必要なエネルギーをしっかり補給することで、低栄養状態を避けることができます。。
まとめ

廃用症候群はさまざまな症状を引き起こしてしまう疾患です。
しかしすぐにできる簡単な対策で、回避することができます。
医師やケアマネジャーとよく相談し、適切な予防法を行うことが重要なポイントです。
無理のない範囲でできるリハビリや食事管理を徹底し、廃用症候群を防ぐよう心がけましょう。