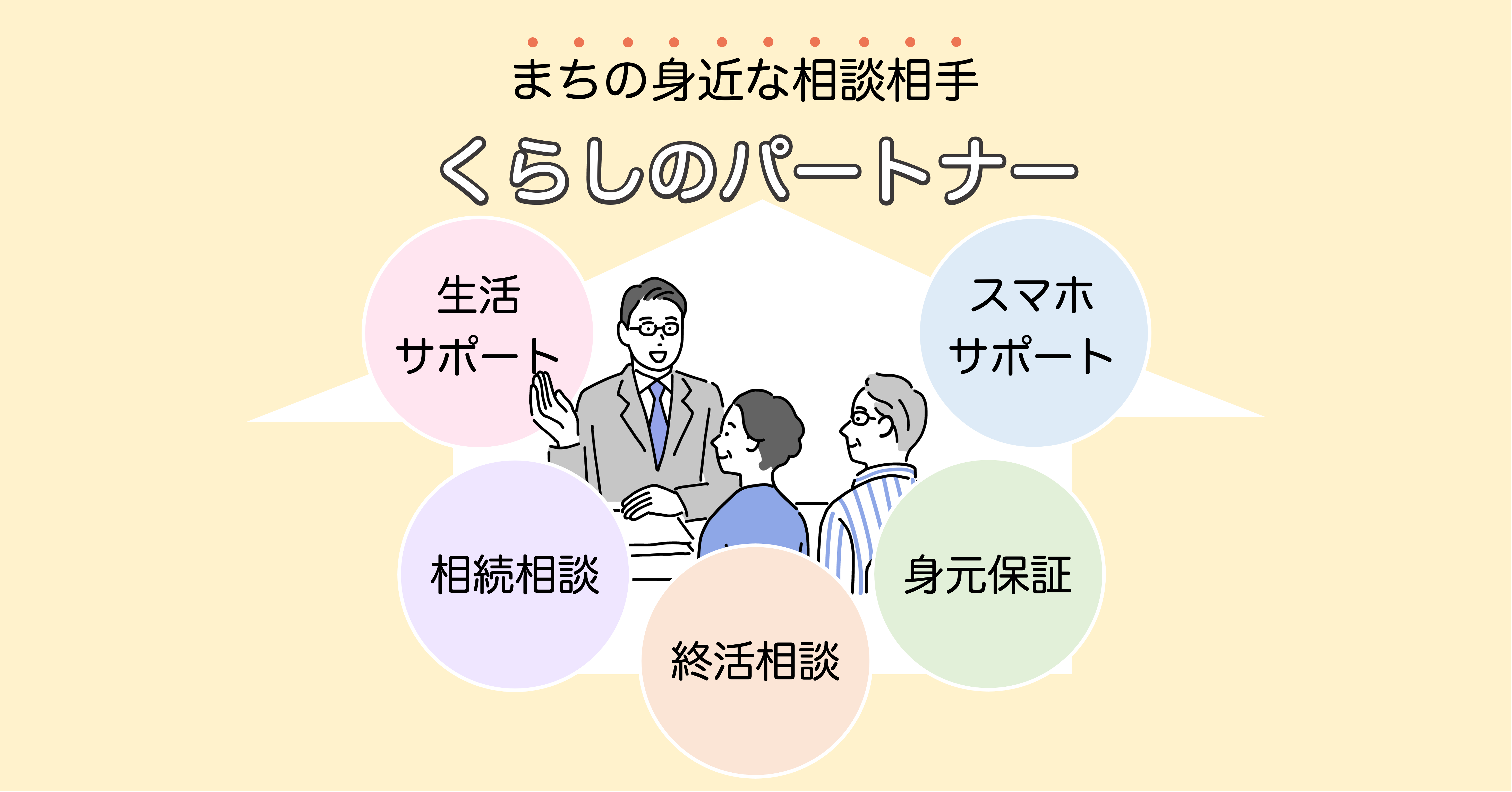家族の介護を在宅で行う場合、要介護者の介護度によっては福祉用具や介護用品が必要になることがあります。
福祉用具・介護用品にはさまざまな種類があり、購入しなければいけないもの、レンタルで対応できるものの2種類があるため、目的やADLによって選択することが必要です。
そこでこの記事では、福祉用具・介護用品に関する基礎知識や選ぶときのポイントなどをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
福祉用具・介護用品が必要になるのはどんな時?

一般的に福祉用具・介護用品とは『高齢者の方の生活をサポートする道具』です。
どんなときに福祉用具や介護用品が必要になるのか、生活のシチュエーション別にご紹介しましょう。
移動時
安全な歩行をサポートしたり、移動を介助するときに必要な福祉用具や介護用品があります。
- 車いす
- 歩行器
- 杖
などがあり、使う方の介護度や住宅環境などによって使用する用具は変わります。
また外出時に使用することなどもあるため、歩行状況をしっかりと確認して選ぶことがポイントです。
睡眠時
ベッドからの起き上がりが困難だったり、ベッド上での生活が長くなったりしたときには福祉用具・介護用品が必要です。
特殊寝台と呼ばれる介護ベッド・電動ベッドなどが該当し、サイドテーブル・マットレス・体圧変換器なども必要になることがあります。
在宅介護を行っている場合は、特殊寝台を利用することで介護者の負担を軽減することも可能です。
入浴時
転倒の可能性が高くなる浴室でも福祉用具や介護用品を利用することが考えられます。
- シャワーチェア
- 踏み台
- バスボード
などの種類があります。
シャワーチェアは介護をする方にとっても負担を軽減して安全を確保できる介護用品のため、利用が多いことが特徴です。
排泄時
在宅介護でもっとも負担が大きいといっても過言ではないのが排泄介助です。
トイレまでの移動介助やトイレ内で利用する手すり、歩行が難しい方のために利用するポータブルトイレなどが必要になることがあります。
便器から立ち上がる際の膝への負担を軽減する補高便座・やわらか便座なども人気で、寝たきりの方の場合は尿器や差し込み式の便器などもあります。
介護保険が使える福祉用具貸与

福祉用具・介護用品は購入するだけではなく、介護保険を利用してレンタルをすることができます。
購入するよりも費用が抑えられることや、介護度に合わせて借り換えができることなどがメリット。
介護保険が使える福祉用具貸与とはどのようなものなのか、詳しくご紹介しましょう。
対象者は?
介護保険を利用した福祉用具貸与の対象者は、要支援・要介護の認定を受けた人になります。
介護度によってレンタルの内容が変わるため、誰でも同じように貸与ができるということではないので注意が必要です。
利用額は?
介護保険が適用されている福祉用具貸与の利用者負担は1割です。
ただし所得によっては2割・3割の場合もあります。
利用限度額は他のサービスとの合算となるため、介護度別の基準範囲内で対応する必要があります。
どんな用具がレンタルできる?
厚生労働省が定めた介護保険を利用して貸与できる福祉用具は、以下の11種類です。

あれば便利だけど購入するには高価すぎるものが多く、介護保険を使うことで費用の負担を抑えて使用することができます。
介護度によって利用対象者が定められているため、ケアマネージャーに相談の上で決めることをおすすめします。
特定福祉用具貸与のメリット・デメリット
福祉用具・介護用品のレンタルのメリット・デメリットをしっかりと理解しておきましょう。
| メリット | デメリット |
費用の負担が少ない 状況に応じて返却・借り換えができる | 新品ではない 返却を考えると使うときに気を遣ってしまう |
介護保険が使える特定福祉用具販売

レンタルではなく、介護保険を利用して購入できる福祉用具・介護用品もあります。
衛生面からレンタルにできないものや品質劣化が考えられるものについては、購入で使用することが可能です。
対象者は?
介護保険を利用するため、介護保険の要介護認定を受けている方が対象です。
購入先は、都道府県の福祉用具販売の指定を受けている事業所からの購入が条件となります。
費用は?
介護保険を利用するため、利用者の負担は1割です。
ただし、要介護度に関係なく年間の利用限度額は一律10万円となっています。
一旦全額負担で購入し、市町村へ申請し認められれば購入費の9割が支給される仕組みです。
どんな用具が購入対象になる?
福祉用具の購入対象となるものは、衛生上他人が使ったものがNGとされるシャワーチェアーなどの入浴補助道具や、自動排泄処理装置の交換可能部などがあります。
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具の部分
- 排泄予測支援機器
福祉用具購入のメリット・デメリット
福祉用具の購入には、レンタルとは異なるメリット・デメリットがありますのでご紹介しましょう。
| メリット | デメリット |
新品を利用できる 柄・色などを自分の好みに合わせることができる | 身体状況の変化に対応することが難しい 費用負担が大きい |
購入?レンタル?介護用品を選ぶときのポイント

購入か、レンタルか…福祉用具や介護用品を選ぶときのポイントはどんなことなのでしょうか?
費用面だけではないポイントも合わせてご紹介します。
高額な介護用品はレンタルを活用
福祉用具・介護用品は思っているよりも高額であることが多いものです。
レンタルに該当するものであれば、まずはレンタルを活用することをおすすめします。
メリット・デメリットでもご紹介したように、レンタルの場合は身体状況の変化に合わせて返却や借り換えが可能です。
高額な商品の場合、何度も購入しなければいけなくなるのは非常に大きな負担になります。
特に初めて使うという場合は、レンタルで試してみてから必要があれば購入するというスタンスで良いでしょう。
介護をする人が楽になる介護用品を
福祉用具・介護用品はもともと高齢者の方の生活をサポートする目的で作られていますが、介護をする人の負担を軽減できるメリットもあります。
福祉用具・介護用品を選ぶときは、介護をする人が少しでも楽になるものを選んでください。
例えば介護用ベッドは高さが調節できたり、足や頭の部分を起こしたりすることができます。
排泄や着替えの介助が必要な場合、介護をする人の身長に合わせて高さを調節するだけでも負担は大きく軽減されるのです。
また徘徊感知機器などは、認知症の方を介護する人にとって心強い味方になります。
身体的・精神的に楽になれるということを選ぶ基準の一つにしてみてください。
住居の状況・ADLに合わせること
在宅介護の場合、住居の状況に合わせた福祉用具・介護用品を選ぶことはとても大切です。
筆者が介護事業所に勤務していたとき、家の廊下がとても狭いにもかかわらず歩行器を使用して、引っかかったために転倒してしまったという利用者さんの話を聞いたことがあります。
住居の状況やADLはケアマネージャーがすべて把握していますので、もし必要だと感じた福祉用具や介護用品があれば、ケアマネージャーに相談しましょう。
レンタルでも購入でも、費用がかかることは同じです。
少しでも無駄を作らないために、入念な準備をすることがポイントといえるでしょう。
まとめ

福祉用具・介護用品は高いと思いがちですが、介護保険を利用することで費用の負担を抑えることができます。
少しでも生活がサポートされるように、介護をする人もされる人も楽に過ごせるように福祉用具・介護用品を活用しましょう。
住環境やADLを考慮することも大切なので、まずはケアマネージャーに相談することをおすすめします。