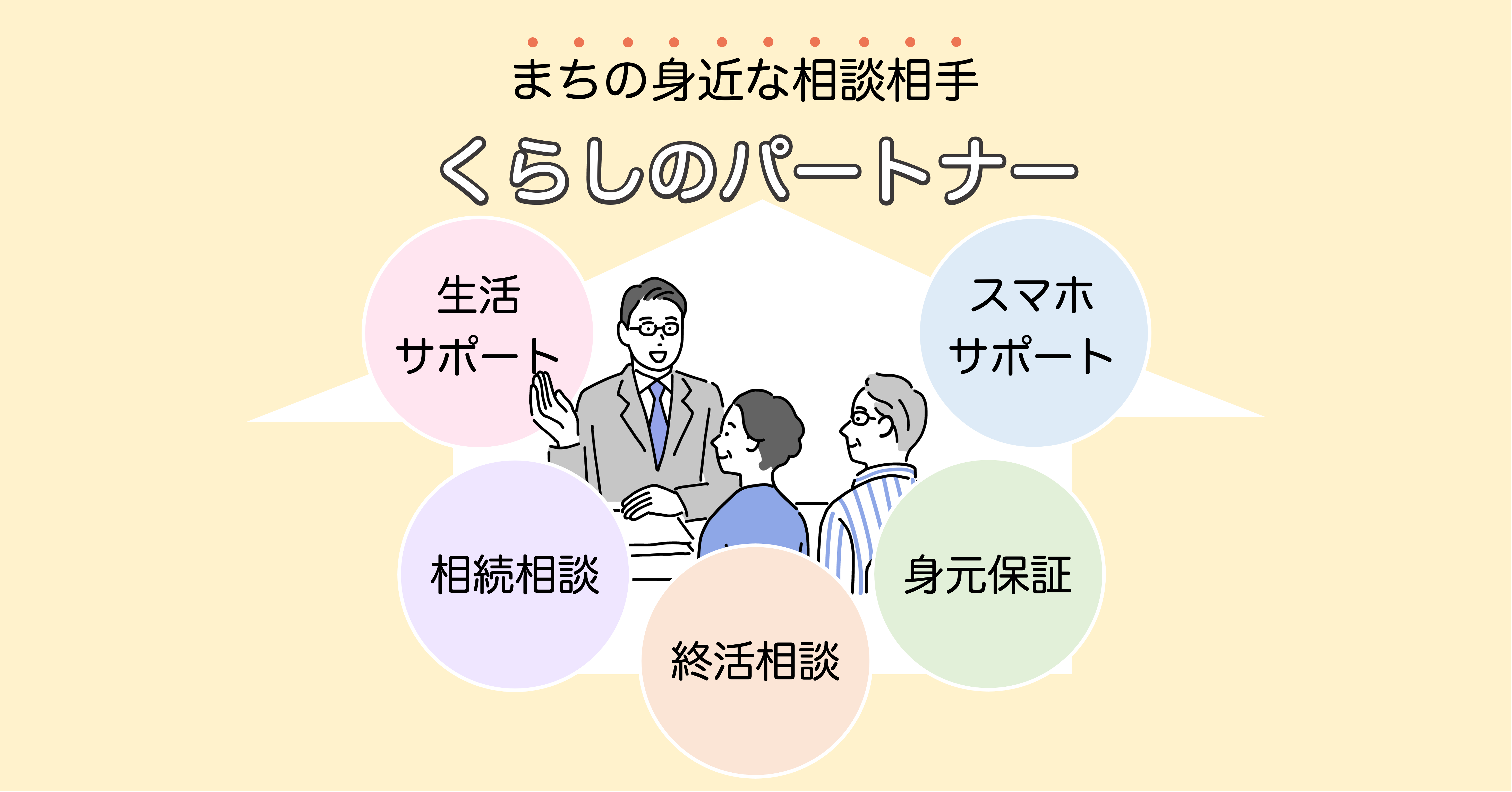介護離職とは、家族・親族の介護のために仕事を辞めることです。
介護離職をして介護に専念できるというメリットがある反面、収入の減少やキャリアの中断などデメリットが大きい手段ともいえます。
特に収入の減少は家族全員の問題となるため、できる限り介護と仕事を両立できる方法を探す必要があります。
この記事では、介護離職をせずに仕事と両立ができる方法の一つとして利用できる、介護休業給付金制度についてご紹介します。
介護離職をする前に、自分が利用できる方法かどうかを見極めるための判断材料として参考にしてください。
介護休業給付金とは?

介護休業給付金とはどのような制度なのでしょうか?
概要や受給要件についてご紹介します。
介護休業給付金の概要
介護休業給付金とは、厚生労働省が下記のように定めた制度です。
| 配偶者や父母、子等の対象家族を介護するための休業を取得した被保険者について、介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に、ハローワークへの支給申請により、支給されるものです。 |
支給される金額は給与の67%で、満額ではありませんが休業期間が終了すれば、職場に戻ることができます。
93日を限度に3回までの分割取得が可能で、同居の家族はもちろん同居・扶養していない祖父母・兄弟姉妹・孫も対象です。
管轄は厚生労働省で、国民年金や健康保険に加入している労働者や公務員などが対象になります。
介護休業給付金は職場復帰が前提となっているため、退職を予定している人は対象外です。
介護休業給付金の受給要件
介護休業給付金の受給条件は、下記の2点です。
- 家族を介護するために「介護休業」を取得した被保険者であること
- 介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること
注意しなければいけないのは、介護休業給付金と厚生労働省の管轄する他の給付金制度は併用できないことです。
産前・産後の休業中などの期間は介護休業とみなされませんので、注意しましょう。
介護休業と介護休暇の違い
介護休業と似た制度に介護休暇があります。
しかしこの2つには違いがありますので、しっかりと押さえておきましょう。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
| 賃金・給付金 | 賃金はなし 介護休業給付金の条件が合えば受給可能 | 賃金はなし ※各会社の規定による |
| 手続き | 書面で事業主に提出 | 特に定めはなし |
| 取得可能日数 | 通算最大93日まで | 年5日(対象家族1人につき) |
介護休業が長期間であるのに対し、介護休暇は短期間(時間単位)でも取得が可能です。
また介護休業は給付金の制度が定められていますが、介護休暇は各会社の規定によって、給付金などの支援がない場合もあります。
介護休業給付金の手続きについて

介護休業給付金の受給資格がある場合は申請を行う必要があります。
どのような手続きが必要なのか、順を追ってご紹介しましょう。
申請先
申請先は、勤務先(事業主)の所在地を管轄するハローワークです。
基本的には勤務先(事業主)を通して申請を行いますが、被保険者本人が申請を行うこともできます。
申請期間
介護休業給付金の申請期間は、介護休業終了日の翌日から2カ月後の末日までです。
介護休業給付金を受け取れるのは休業期間が終了してからになることを覚えておきましょう。
必要な書類
介護休業給付金に必要な書類は、下記のように定められています。
| 【受給資格確認に必要な書類】 1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類) 【支給申請に必要な書類】 1.介護休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。 2.被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 3.住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類) 4.出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類) 5.賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類) |
勤務先への申請の際に、必要な書類についても確認をしておきましょう。
介護休業給付金制度を利用するときの注意点

介護休業給付金制度を利用する際には、注意したいポイントがあります。
主な3つの注意点についてご紹介しましょう。
複数人が介護する場合
介護休業給付金制度では、一人の被介護者を複数人が介護をすることが認められています。
家族間で同じ時期に取得したり、時期をずらして取得したりすることも可能なため、家族間でよく話し合い、お互いにべストのタイミングで取得ができるよう調整することがポイントです。
休業期間が短い場合
介護休業給付金受給の対象となる条件として、『2週間以上の常時介護が必要な状態』とありますが、これは介護休業の期間を指したものではありません。
そのため、介護休業の期間が2週間以上である必要はありません。
2週間という期間は被介護者が常時介護を必要とする期間を指すもので、入院などで加療が必要な場合は被保険者本人が介護休業を取得する必要がなくなることもあります。
休業期間が短い場合でも、介護休業給付を受給することは可能です。
給付金が支給されるタイミングについて
介護休業給付金が支給されるタイミングは、介護休業の期間終了後です。
申請期間の項でもご紹介したように、介護休業給付金の申請は、介護休業終了日の翌日から2カ月後の月末までとなっています。
介護休業給付金で支給される金額は給与の67%です。
そのため、介護休業期間にかかる費用や生活費に関しては、事前に準備しておく必要があります。
介護休業給付金に関するよくある質問

介護休業給付金に関するよくある質問をまとめました。
厚生労働省のQ&Aをもとに、いくつかの質問をピックアップしてご紹介しましょう。
Q・有期雇用労働者の場合、受給要件は異なる?
契約社員や嘱託社員など、有期雇用労働者の場合は一般の無期雇用労働者とは受給要件が異なります。
有期雇用労働者は、無期雇用労働者の受給要件に加えて、下記の要件が必要です。
| 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと |
Q・同じ対象家族について複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合、それぞれに介護休業給付金を受けることは可能?
可能です。
それぞれが受給要件を満たしていれば、介護休業給付金を受給することができます。
Q・介護休業給付は、課税の対象となる?
介護休業給付金は課税対象とはなりません。
Q・介護休業給付の支給申請は誰が行う?
介護休業給付金の申請手続は、原則として勤務先の会社(事業主)を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
まとめ

家族の介護は、想像よりも過酷なものです。
いっそのこと仕事を辞めて専念したいと考えることもありますが、介護離職はデメリットが多いことも理解しておかなければいけません。
受給要件に該当する場合は、まず介護休業給付金制度の利用を検討してみましょう。
同じ被介護者に複数人で対応することも認められている制度です。
家族で協力し、収入減少やキャリアの中断をしなくても良い方法を見つけることがポイントといえるでしょう。