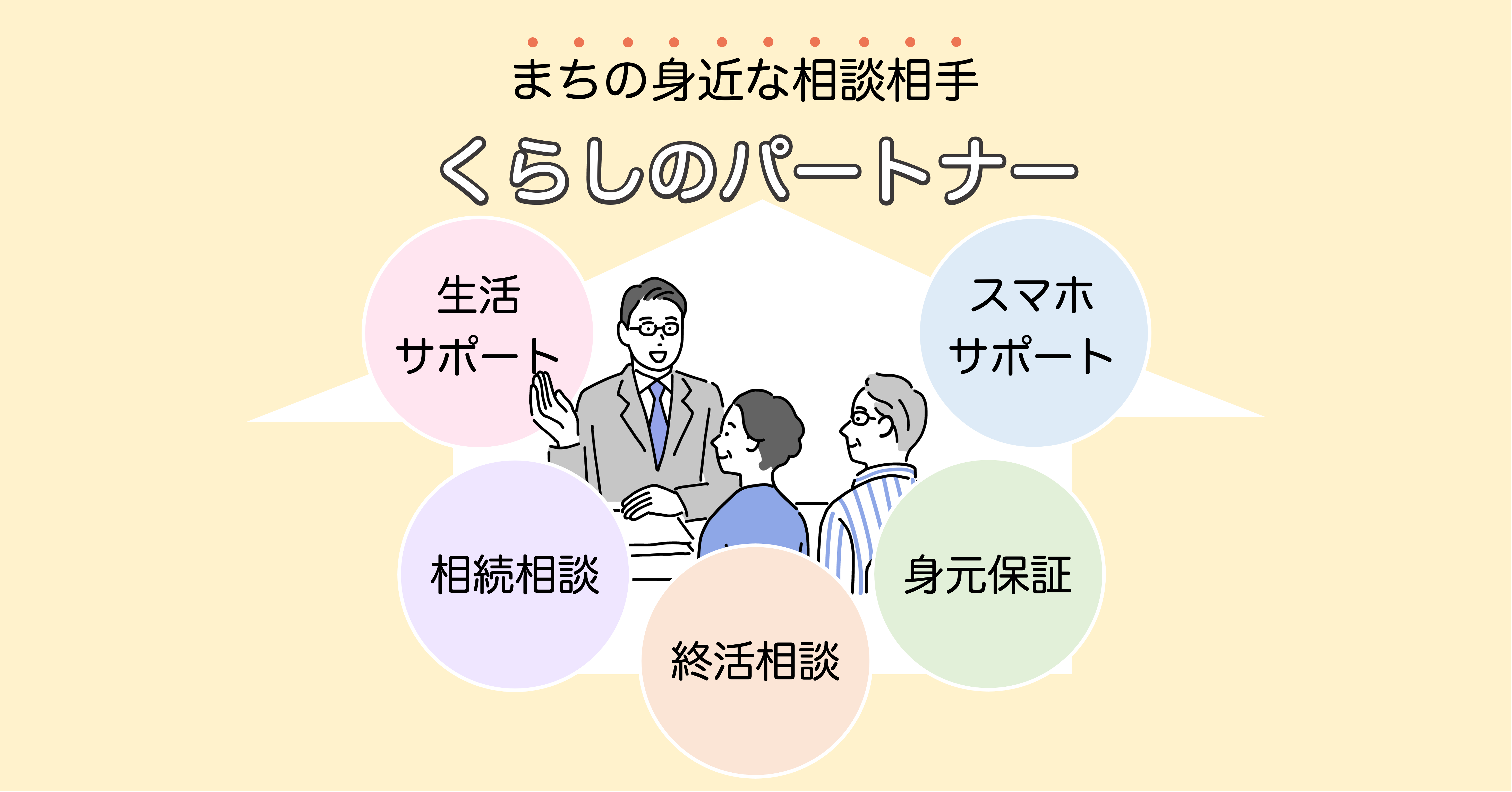要介護1や2になると、自力歩行は可能だけどふらつきがあり、転倒・転落の危険性があります。
または、少し長い距離になると車椅子がいいのではないか?と考えるようになってきます。
勿論、自立や要支援の人であっても、足腰が弱り、歩行中にいつどのようなタイミングで転倒・転落するかは分かりません。
そのために、リハビリテーション(機能訓練)があり、いつまでも今持っている機能を継続・向上するために行います。
とはいっても、家族であれば歩行が難しい親等に対して、どのように方法で対応するのがベストなのか悩む人も多いと思います。
今回は歩行困難な高齢者に必要なのは歩行訓練(リハビリ)なのか?もしくは車椅子に乗ってもらうのが良いのかを解説します。
歩行困難になる理由
まず、おさえておかなければならないのが、歩行困難になる理由です。
歩行困難になる理由として、主に2つあります。
①下肢筋力によるもの
②疾患によるもの
です。
①下肢筋力低下によるもの
加齢によって筋力が衰え始めたら、機能訓練(リハビリ)をしないでいるとその症状はどんどん加速していき、やがては車椅子生活となることが予想されます。
そうならないためにも、筋力低下を感じるようになる前の段階で、なんらかの機能訓練を行う必要があります。
②疾患によるもの
歩行するためには、ただ単に足の筋肉を使うだけではなく、脳が命令を出し、その命令を伝える神経の働きが必要になります。
そのため、歩行困難の原因には筋肉組織や骨組織そのものの損傷だけでなく、脳組織、神経組織の影響を受けている疾患もあります。
例えば・・・
■脳梗塞により麻痺
■関節リウマチ
■パーキンソン病
■筋萎縮性側索硬化症
などがあります。
結論はどちらも!
歩行困難になった場合、『歩行訓練』をした方がいいのか?それとも『車椅子』にした方がいいのか?というのが今回のタイトルにもなっていますが、結論から言えばどちらも重要ということです。
「一体どういうこと?」と考える人もいらっしゃるかと思うので解説します。
歩行訓練のメリット・デメリット
歩行訓練を行う理由として2つあります。それは・・・
①機能の維持
②機能の向上
です。
当たり前ですが、歩行訓練をすることによって「歩けなくなるようにしよう」と考えて行う人はいないでしょう。
いわばリハビリ(歩行訓練)は希望なのです。
高齢になったり、若い人でも病気に罹患することで歩行が難しくなってしまうと「もうこのまま歩けなくなるんじゃないか・・・」と不安に思うようになる人も珍しくありません。
そうなると精神的にもマイナスに作用し、ふさぎ込んでしまいます。
『歩行訓練を習慣化する』『日課に入れる』ことによってそれが生活の一部になり、なくてはならいものになるのです。
これが、最大のメリットだと私は考えています。
歩行訓練のデメリットをあえて言うならば、以下のようなことが挙げられます。
①転倒のリスクが高まる場合がある。
歩行訓練をすることによって、訓練の成果が出て、自信も付くでしょう。
危険性の理解が難しい場合、自信の方が先行してしまい、十分な機能が回復しないまま歩こうとしてしまいて転倒する可能性があります。
特に、認知症のある人と、リハビリに対する意欲が高すぎる人は注意が必要です。
②オーバーワークになる可能性がある。
施設や病院で歩行訓練を受けている場合には、常勤スタッフによって見守りがあるのでそれほど心配はいらないと思います。
しかし、在宅介護などにおいて、一人や家族だけの生活する時間が長くなれば、歩行訓練の負荷が強くなりすぎて、それにより筋肉や関節を傷めてしまう可能性もあります。
歩行訓練のやりすぎに注意が必要です。
車椅子使用のメリット・デメリット
下肢筋力低下の度合いによって、車椅子を使うか、使わないかを判断します。
これは、リハビリの専門職(理学療法士等の医療従事者)によって判断されるのが理想です。
こんな場合には車椅子使用を
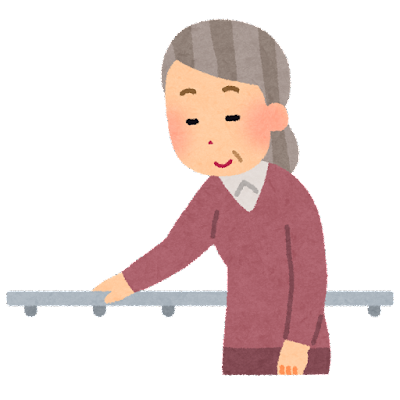
例えば、室内(自宅内)は手すりや壁伝いで歩行することが可能であっても、屋外に出るとバランスを崩した時、頼るものがないことが多いです。
屋外で転倒したら、室内で転倒するよりも骨折や怪我をするリスクは高くなりますので、念のため安全重視で車椅子を使用する方法が選択されることがあります。
また、向精神薬を服用している場合には、副作用として足元のふらつきが起こる場合があります。
特に眠る前に薬を飲んで夜間充分眠れた後、朝方になっても薬の効果が残っている場合にふらつきがみられます。
そんな時に一時的に車椅子を使用することがあります。
さらに、なんとか歩行はできるけど、距離が長くなると途中で疲れる場合などに車椅子の使用が勧められます。
車椅子は移動手段と考える

車椅子に一度座ったら、そのまま食事をしたり余暇活動をしたりすることもあるかもしれません。
しかし、車椅子は移動手段であり、適切な座位を保持するためのものではないことを抑えておきましょう。
車椅子で移動した場合にはそのまま座り続けるのではなく、椅子やソファーに座り替えて、一人ひとりのあった座位保持をしなければなりません。
そういった意味では、車椅子→移動→椅子(ソファー) の一連の動作が億劫に感じてしまうこともあるでしょう。
また、本人や家族は「歩行困難だけどなるべく訓練をしなければならない」と思う気持ちがあっても、車椅子という便利が道具があることによって、自主的な歩行訓練をしなくなる可能性も否定できません。

上記のような留意事項をクリアできれば、車椅子と歩行を併用することによって転倒・転落のリスクも減らしながら下肢筋力の維持・向上ができることになるでしょう。
症状によっては歩行訓練ができないこともある
冒頭で解説させて頂いたように、単に筋力を鍛えれば歩行機能の維持・向上が期待できます。
しかし、歩行困難を引き起こす病気を発症した場合には、歩行訓練よりも優先して行わなければならないこともあるのです。
例えば『筋萎縮性側索硬化症』
難病指定のこの病気は、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん痩せて力がなくなっていきます。
具体的は症状として・・・
■ 手指の使いにくさや肘から先の筋肉が痩せる
■ 力が弱くなる
■ 話しにくい、食べ物がのみ込みにくい
■ 足の筋肉が痩せて力が弱くなる
などでの症状で始まることもあります。
通常左右いずれかから症状が出現しますが、
■ 両側の肩周りの筋肉が痩せる
■ 力が入らない
症状から始まることもあります。
どこから症状が始まった場合でも、やがては呼吸の筋肉を含めて全身の筋肉が痩せて力が入らなくなり、身体を動かすことが難しくなります。
『歩行が難しい気がする』と思った段階で、歩行訓練を行ったとしても、病気の性質上筋力を向上させることは難しいのです。
悲観的になってしまう気持ちも十分理解できますが、このような場合には医療とリハビリと相談して、先を想定した対応も含めて取り組んでいきましょう。

イラストのようのコミュケーションツールを使いこなせる練習等も行うことも重要でしょう。
※歩行訓練を含めて『筋萎縮性側索硬化症』と診断されても、全てのリハビリを否定するものではありません。
まとめ
歩行困難になった場合、歩行訓練も車椅子の使用も必要になってきます。
重要なの・・・
■どの程度の歩行訓練をするのか
■どのような方法で歩行訓練をするのか
■歩行訓練の頻度はどうするか
■車椅子を使うタイミングはどうするか
■どのような場面で車椅子を使用するか
など具体的な内容です。
本人や家族だけで決めるのではく、担当のケアマネジャーを含めて、リハビリの専門職(理学療法士や作業療法士)や医療従事者と相談し、実施していくようにしていきましょう。
そのためには、介護保険サービスの利用は必須です。
歩行が困難になったなと感じたら、役所や地域包括支援センターなどへ相談してください。