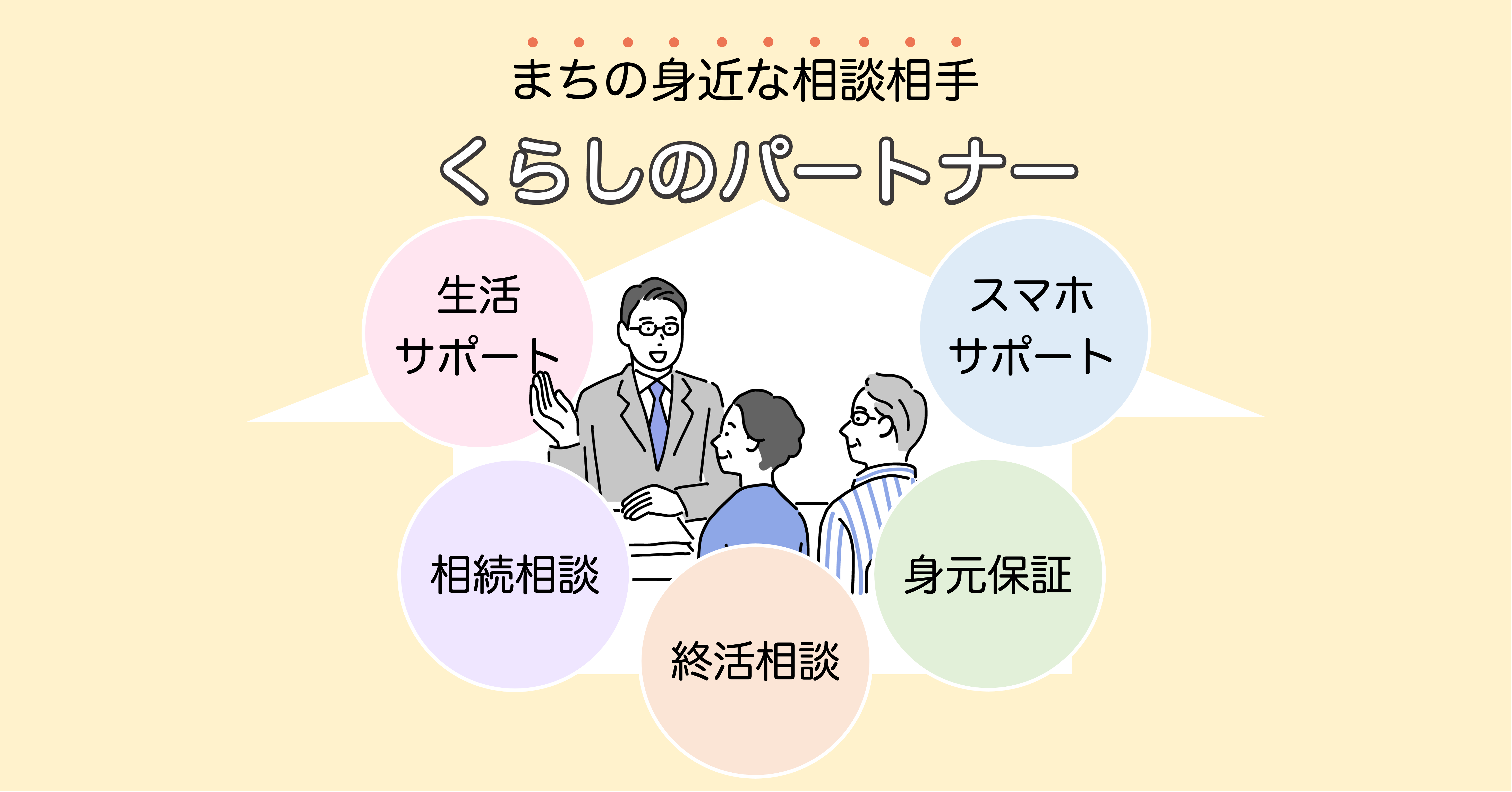在宅介護から施設介護に切り替えると、施設のスタッフと良好な関係が築けなければ、何かと不安な気持ちになるでしょう。
介護保険制度は『契約』によって利用が開始されます。
それは施設利用においても同じで、入所前あるいはその前々から契約を行って、入所の意思の確認やお互いに思い違いが無いかの確認を行います。
施設側が果たさなければならない業務としては、
■介護
■看護
■栄養管理
■権利擁護
■相談支援
等がありますが、これらがしっかりと行われているのは大前提として、今回のお話をさせて頂きたいと思います。
サービスを提供する事業所(介護保険施設等)側から、敬遠されやすい家族についてを解説いたします。
施設と良好な関係を築くための一つの参考にして頂ければ幸いです。
①連絡が取れない家族

契約の際、第2~第3連絡先まで求められることが多いと思いますが、場合によって職場の連絡先も求められることもあります。
では、なぜそこまで連絡先について施設はこだわるのでしょうか?
それは命に関わるような場面になった時、施設職員では判断できないからです。
例えば、契約の際、「延命治療はしません」という言葉が家族からあったとします。
いざ、それまで異常なく生活されたいた利用者が急変した場合、それでも家族の「延命治療はしません」という言葉に心境の変化がないか確認する必要があるのに、すぐに連絡がつかなければ施設は困ってしまうのです。
よってキーパーソンを中心に、その他の家族とも連絡を取りやすくしておく必要があります。
仮に海外旅行に行く際は「一週間ほど日本にいませので、何かあっても駆けつけることはできません。代わりに次男の〇〇に電話して下さい。」等の対応をすると良いでしょう。
②約束を守れない家族
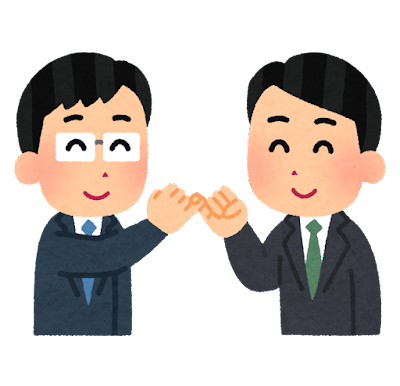
少なくとも契約書や重要事項説明書、書面で渡されるプリントに記載されている『家族へのお願い』についてはよく内容を確認し、約束事を守るようにしましょう。
特に健康に関わるよなことをする家族には施設は悩むことが多いでしょう。
例えば夏の暑い時期に『生もの差し入れはお控えください』と言われているにも関わらず、面会の際にそっと本人に食べさせたりすると、食中毒のリスクを高めてしまいます。
他にも、家族のサポートで外出した際に食事をしたにも関わらず「なにも食べていません」というような発言があると、施設はそれを当然信じてしまいます。
しかし、その晩の夕食の摂取量が極端に少なければ「体調に異変があるのでは?」心配することになり、家族に「外出中変わった出来事はありませんでしたか?」確認するでしょう。
そんなとき「実はドーナツとたこ焼きを食べていて…」という話になると、施設は家族に対して少しずつ不信感をつのらせていきます。
約束事はしっかり守って、施設との信頼関係を構築できるようにするといいでしょう。
③集団生活を受け入れない家族

例えば、グループホームであれば1ユニットでも最高で10名の利用者がそこで生活します。
特養や老健であれば、100名もの利用者が生活する施設もあります。
当然のことながら、利用者には施設での生活や療養に慣れて頂くように、施設側は少しの努力も惜しまないでしょう。
しかし、どうしても在宅介護と施設介護とで同じようにできないことがあります。
それは、生活環境です。
全ての利用者にはそれぞれの特性や性格、疾患等あり、個別化された関わり方をすることになりますが『集団生活の場』という環境だけはどれだけ努力をしても替えることができません。
■一人だけ献立の違う食事の提供を望まれる。
(苦手な食べ物をやめて別のものにする・嚥下しやすい軟らかいものにする等ではなく、献立そのもの変更を望まれること)
■認知症や精神疾患がないにも関わらず、他の利用者に迷惑な行為を行うこと容認して欲しいと言われる。
■新型コロナウイルス等の感染症を発症した場合、隔離に同意してくれない。
このような事柄に関しては、『集団生活』という観点から、施設としてはどうしても対応できないのです。
この辺りを受け入れられない家族は、施設に敬遠されることがあります。
④施設にケアを任せられない家族

多くの家族が、在宅介護に限界を感じて、意を決して『施設介護』を選択することになるでしょう。
これまで、一生懸命自宅で介護をされてきた『家族の想い』は十分施設も理解してくれるはずです。
しかし施設介護を選択するということは、ある程度のことは施設にお任せするという認識でいないといけません。
例えば、
■ オムツの種類に指定がある家族
■ 褥瘡などの処置に対して、自己流の方法を依頼してくる家族
■ 処方の内容に不満を持ち、別の薬を依頼する家族
(医師は医療の専門職であり、疾病などから判断して出される薬ですので、家族がそれに対して別の薬を依頼して、医師がそのままそれを受け入れることは、法的にも認められません。「同じ効用でそれに代わる薬はないですか?」等の質問で相談すると良いでしょう。)
『在宅介護』から『施設介護』に切り替えて不安な気持ちはあると思いますが、『施設介護』と決めた時点で、ある程度のケアは施設にお任せするという気持ちでいるほうが、お互いに信頼できる関係が築きやすいと思います。
施設に対して、
〇こうして欲しい
〇こうなればいい
〇これは止めて欲しい
などの要望があれば、一方的にお願いするのではなく『相談』という形から入っていくと、施設側も快く要望・意向にそった支援を検討してくれるでしょう。
⑤威圧的に発言する家族

冒頭でも説明した通り、介護保険制度は『契約』によってサービスがスタートします。
本人や家族は料金を支払い、サービスを受ける権利が発生します。
そうなると、しだいにサービスを過剰に要求するようになり、自分たちの思わぬ出来事が起こると、冷静になれず威圧的な態度で、家族の意向を通そうとする家族もいらっしゃいます。
『嫌がらせ』のような過剰な要求は『カスタマーハラスメント』として扱われ、場合によっては弁護士に相談することもあります。
施設側に不手際があったとしても、なるべく平常心を保ち、問題を解決することを念頭に置いて施設に伝えるようにしましょう。
施設側はきっと真摯に受け止めて対応してくれるはずです。
意外にOK!こんな家族は歓迎
実は、一般的に考えると施設から敬遠されるのでは?というようなことでも、施設にとっては嬉しいこともあります。
それは『苦情』です。
『苦情』と聞くと、マイナスなイメージが強いかもしれません。
しかし、『苦情』は今の施設のマイナス面を改善するための良い意見になるのです。
正式に苦情相談窓口に申し出しなくても、面会の際や日常の何気ない場面で、自分たちの考えや想いはしっかり伝える方が感謝されます。
それを参考に施設にとって『マイナス』であると判断されれば、組織として改善され、その後の利用者や家族に対しては『プラス』な状態で運営がなされるでしょう。