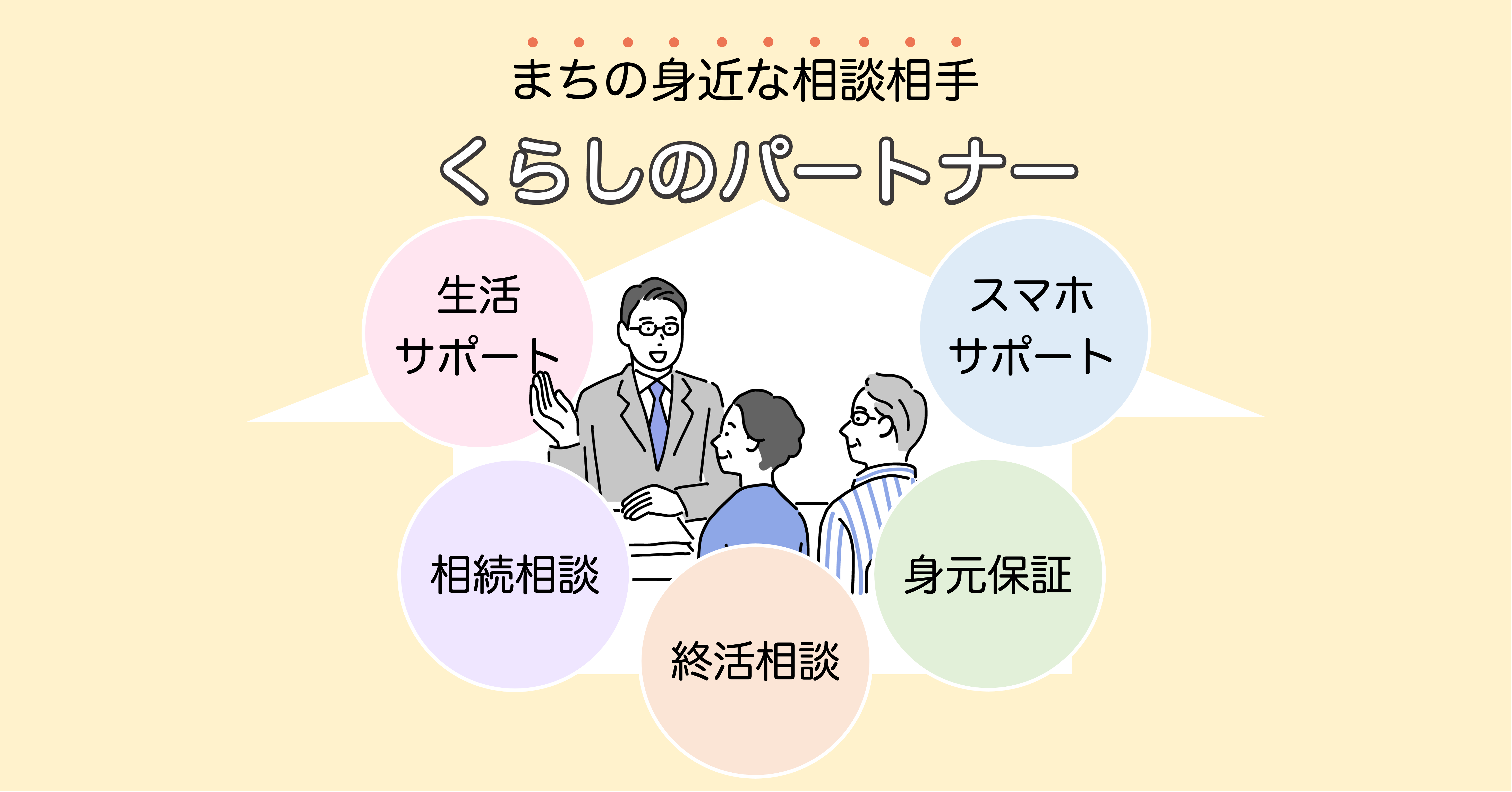自宅で親などの介護をしていると
「このやり方でいいのだろうか?」
「もっといい方があるのでは?」
「本当に本人のためになっているのだろうか?」
等、悩むこともあるかもしれません。
そんなときに一番の頼りになるのが、担当のケアマネジャーですが、なかなかすぐに連絡をしないケースもあります。
そんな時に思い出していただきたいのが、今回ご紹介する『介護の3原則』です。
これは、高齢者の幸福感が世界一高い国として知られるデンマークで提唱された考え方なのです。
『介護の3原則』を念頭に置いて、普段からケアをするようにすれば、悩んだ時に参考になると思います。
どうぞ最後までご覧ください。
【介護の原則①】生活の継続性

今の生活をなるべく長く継続させるという原則です。
今の生活というのは、例えば・・・
■屋内なら歩けるが屋外や長距離になると車椅子が必要な生活
■食べこぼしはあるが何とか自分で食べることができる生活
■ベッド上での生活が主だけれど、褥瘡など皮膚トラブルがない生活
■週に2回のデイサービスを利用している生活
など、とにかく『今』の生活をなるべく長期に渡り維持させることが大切なのです。
生活を維持させるということは、まずは本人の身体状態が低下しないようにする必要があります。
身体状態を低下させないために、家族ができることとして、以下のような事柄があります。
本人の身体状態を低下させない

①異変があれば受診・往診を依頼する。
②処方された薬は自己判断で増量・休止等せず継続して服用する。
③食事・水分をしっかり摂取できるよに支援する。
④排便のコントロールや観察を行い、異変があれば看護師や医師に相談する。
⑤褥瘡にならないように(悪化しないように)皮膚の観察を行う。
⑥誤嚥性肺炎予防のために、しっかり口腔ケア(歯磨き等)を行う。
このようなことがあります。
勿論、家族だけ行うのは難しいので、担当のケアマネジャーと二人三脚で取り組むように意識しましょう。
本人の生活環境を変えない

本人の生活環境を変えないで継続させることも大切です。
生活環境を変えないといっても、案外難しいものですし、本人にとってプラスになるかどうかを考えながら検討していかなければなりません。
例えば、食事や水分の摂取が難しい状態であれば、そのままの状態を継続するのは良いことではありません。
人間にとって、衣食住は必要最低限生活を営む上で必要ですし、栄養が摂取できない環境を変化させることができるのなら、積極的にその方法を取り入れなけらばなりません。
『今できていることを悪化させない』という視点で、生活環境を変えないようにします。
例えば・・・
■認知症予防・悪化のため、著しく生活環境を変化させるような引っ越しをしない
■折角、良眠傾向にあるのに寝具を替えない
■安全に座位保持できるのに、むやみに車椅子を替えない
■支障なく歩行できるのに、装具や靴等を替えない
■家族の都合だけで主治医やケアマネジャーを替えない
などがあります。
【介護の原則②】自己決定の尊重

生きていたら当たり前のことですが、『自分のことは自分で決める』ということです。
それは、人間が生まてながらにして持つ、『基本的人権の尊重』から来る、『自己決定の権利』なのです。
例えば、小学校に入学する前にランドセルの色を決めるために、親が子に「どの色が良い?」と尋ね、それを選ぶこともそうですし、職業を選択する場合にも誰から決められるわけでもなく、自分自身が決めることも同じです。
高齢になり、やがて介護が必要となっても『自分のことは自分で決める』という考え方は同じで、家族もそれに寄り添いながら支援をすると心が通う『介護』ができるでしょう。
普段行う家庭での介護を例にとると・・・
①服は自分で選択してもらったものを着用してもらう
②食事を食べる順番は、介護者が一方的に口に運ぶのではなく尋ねながら食べてもらう
③水分補給を行う際、オレンジジュースかカルピスどちらがいいのか選んでもらう
④おやつはチョコレートかビスケットどちらがいいか選んでもらう
等があります。
どんな些細なことでも、『本人に選んでもらう』という気持ちを持ってケアを行うと、心の通った信頼関係ができるはずです。
【介護の原則③】残存能力の活用

残存能力という言葉は少し以前の言葉かもしれません、いまでは『潜在能力を引き出す』という、より『プラス』な考えになっています。
★残存能力の活用とは
今行えている能力を活用して、他の生活の場面にもどんどん利用していくことです。
★潜在能力を引き出すとは
これは主に施設などにおいて、プロが行うことです。
「ここまでの機能・能力があるのなら、もしかしたら〇〇〇も出来る可能性がある」と考えて、これまで使われていなかった能力を引き出すのです。
やがて、それは『生活』という実践の場で利用されるようになり、本人の自信にも繋がるでしょう。
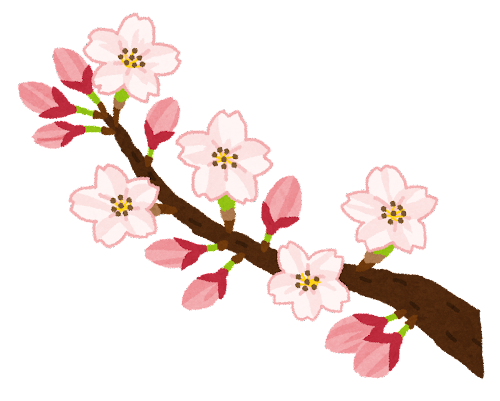
さて、家族が潜在能力の引き出しもしないかというと、それは必ずしもそうではありません。
潜在能力を引き出せるかどうか?の判断は、やはりリハビリや介護・看護のプロすることが多く、
家庭では行うのは難しいと思います。
よって、家庭でできる『残存能力の活用』というところに焦点を当て、支援すると良いでしょう。
具体的には・・・
①風呂に入って、全ての洗身を介護者がしてあげたいという気持ちを押させて、出来る範囲で自分でやってもらう
②食事で多少時間がかかっても、食事介助をするのではんく、本人が最後まで食べるのは見守る
③トイレにいったあとの後始末として、紙でふき取ってあげたい気持ちを抑え、なんとか自分でふき取りができるのあれば、それは本人に任せる
このような些細なことからでも、『残存能力の活用』を支援するように意識すると良いでしょう。
介護の3原則についてプロはどう考えているか
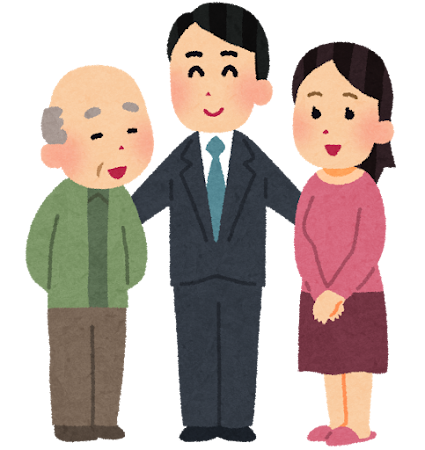
介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員を保持するプロが考える、『介護の3原則』ですが
介護施設においては、ごく自然に行われていることなのです。
ただ、『在宅介護』という場面で、介護する人が家族であればお互いに甘えが生じる可能性があります。
時として、その甘えは、生活の質(QOL)を落としていくことも考えられます。

大前提として、在宅介護をしているだけでも凄いことです。
日々、一生懸命介護をしているときに『介護の3原則』を考えながらケアにあたるのはとても難しいと思いますが、ふとした瞬間に思い出していただいたら幸いです。