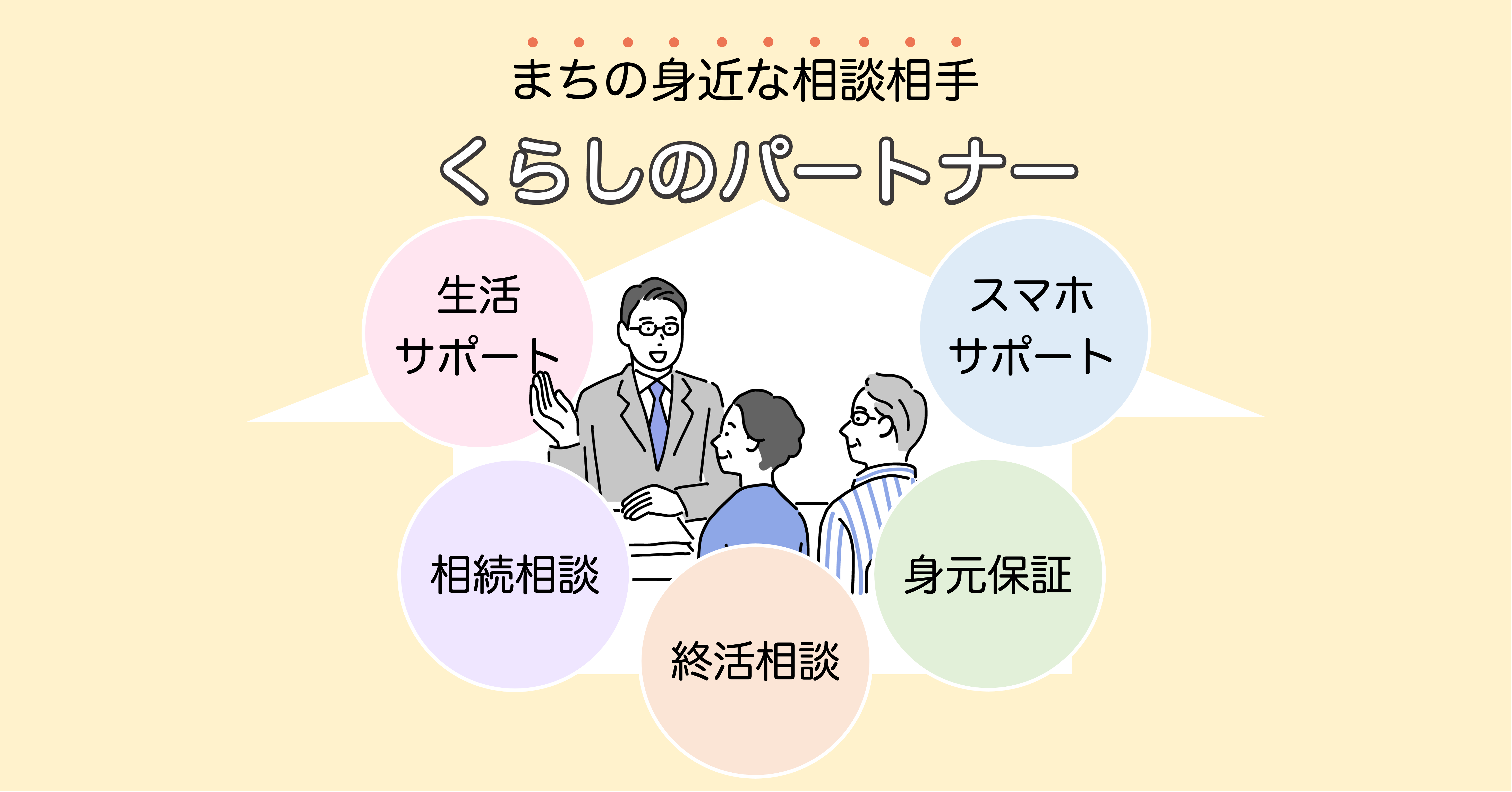久しぶりに実家へ帰省したら、家の中がゴミだらけになっていた…
高齢の親を持つ世代の人に起こりがちなトラブルの一つに、高齢者宅のゴミ屋敷化問題があります。
『昔は綺麗好きだったのに』『前に来たときは平気だったのに』
特に家族が遠方に住んでいる場合や、一人暮らしをしている方の場合は、ゴミ屋敷化してしまうリスクが高くなることが特徴です。
この記事では、高齢者の家がゴミ屋敷化してしまう原因と対処法について、わかりやすく解説します。
対岸の火事と捉えず、万が一のことも想定した上でぜひ参考にしてください。
高齢者の家がゴミ屋敷化してしまう5つの原因

高齢者の家がゴミ屋敷化してしまうのには、原因が必ずあります。
どんなことが原因として考えられるのか、主な原因を5つご紹介しましょう。
①セルフネグレクト
セルフネグレクトとは、高齢者が自身の基本的なケアや必要な生活活動を放置してしまうことです。
具体的には、高齢者が自分自身の食事・身体的な清潔・医療ケアの受け入れ・適切な衣服の着用・住居の保守などを無視してしまうことなどが挙げられます。
セルフネグレクトの場合は、ゴミを捨てずに溜め込んでしまうことが多くなり不衛生な環境になっても、本人は気にしていないことがほとんどです。
セルフネグレクトは身体的・精神的・社会的側面において現れる可能性があります。
②判断力の低下(認知症)
高齢者のゴミ屋敷問題に深く関わっているのは、認知症の発症による判断力の低下です。
今までは普通にできていたゴミ出しや分別などができなくなり、曜日や日にちの認識も難しくなるため、『ゴミの日にゴミを出す』ということができなくなります。
知らないうちにゴミが溜まってしまうことにも無頓着になってしまうことは、認知症などによって引き起こされる判断力の低下が大きく関わっています。
③精神疾患
ゴミ屋敷になってしまう原因としては、認知症以外の精神疾患も考えられます。
- ためこみ症
- 買い物依存症
- うつ病
- 統合失調症
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- アルコール依存症 など
以前から疾患がわかっている場合には対応が可能ですが、一人暮らしなどで知らない間に発症している場合は、精神疾患が原因でゴミ屋敷になってしまう可能性があります。
④もったいない精神
戦争や戦後を経験している高齢者にとっては、『物を大切にする』という精神が根強く残っていることがあります。
『まだ使えるからもったいない』『今は使わないけどいつか使うはず』などと物を捨てないことが特徴。
物を大切に扱うことはとても大切なことですが、壊れた物や使わない物などを捨てないことで、どんどんと不要な物が溜まってしまうのです。
⑤体力・気力の低下
年齢を重ねることで体力や気力が低下し、ゴミ屋敷化してしまうケースも少なくありません。
高齢になると足腰が弱くなり、痛みを伴う疾患を発症することが多くなりがち。
『足が痛い』『膝が痛い』『重い物が持てない』などという症状があると、ゴミ出し自体が億劫に感じるようになります。
また分別の細かい地域では、分別を面倒に感じてしまうことも多いものです。
捨てようと思ったけど、どう分別しいつゴミが出せるのかなどを管理できない…という状況になってしまうと、知らない間にゴミ屋敷になってしまいます。
高齢者の家がゴミ屋敷化したときのリスク

ゴミ屋敷は見た目だけではなく、そこに住む高齢者にとって非常にリスクが高いことをご存知でしょうか?
高齢者のゴミ屋敷化が進んでしまった場合、どんなリスクがあるのかについてご紹介します。
健康被害
ゴミ屋敷のリスクとしてもっとも深刻なのが、健康被害です。
ゴミを捨てないことによる環境の不衛生は、害虫の発生やアレルギーの誘発などの健康被害が考えられます。
最悪の場合、健康被害によって命の危険にさらされる可能性もゼロではありません。
ネズミやダニなどはアレルギーや病原体の感染症などを引き起こすことがあります。
気付かないうちに害虫・害獣が発生してしまうことによる健康被害は、絶対に避けなければいけないリスクと言えるでしょう。
火災・転倒などの事故
ゴミ屋敷を想像してみてください。
うずたかく積まれたゴミ袋や段ボール、不要になった家具や家電、残った食べ物や飲み物…
『足の踏み場もない』という状態であれば、火災や転倒などの事故を引き起こすリスクがあります。
埃がコンセントに溜まることで起こるトラッキング火災やストーブからの引火、最悪の場合は放火の被害に遭うことも考えられるのです。
足の踏み場もないという状況では、家の中での転倒による骨折などもあるでしょう。
不要なゴミが家の中に散乱している状態は、思わぬ事故を招く可能性が高くなります。
近隣からの苦情
ゴミ屋敷は、近隣にも大きな迷惑をかけることになります。
- 悪臭
- 害虫・害獣の発生
- 火事による類焼
- ゴミの散乱
- 治安の悪化
好意的に声をかけてくれる人ばかりではありません。
中にはゴミ屋敷の高齢者と近隣住民がトラブルになるというケースも報道されています。
家族が離れて暮らしていればなおさら、近所の方とのトラブルは避けたいものです。
高齢者のゴミ屋敷化を防ぐための具体策

高齢者のゴミ屋敷化は、必ず何かしらの原因があります。
手遅れになる前に、ゴミ屋敷化を防ぐ対策を考えましょう。
具体的な方法を4つご紹介しますので、できるものから取り組んでみてください。
頻繁に交流する機会を持つ
高齢者世帯のゴミ屋敷化を防ぐためには、高齢者の方と頻繁に交流する機会を持ちましょう。
家族や親戚が分担して定期的に訪問することで、『人が家に来る』という意識が生まれ、『片づけなくては』という行動に繋がることがあります。
ゴミ屋敷になってしまう原因の一つとして考えられるのは社会からの孤立や関係性の希薄です。
『誰も家に来ない』『誰とも話さない日が多い』という状況は、ゴミ屋敷化を加速させます。
家族や親戚が訪問できない場合は、介護サービスなどの利用を検討しましょう。
ゴミ屋敷のリスクを伝える
認知症などを発症していないのであれば、ゴミ屋敷がどんなリスクを抱えることになるのかをきちんと伝えることも予防策の一つです。
『ご近所に迷惑が掛かる』『火災や転倒など事故の危険性が高まる』という具体的な内容は、高齢の方でも十分に理解できるものでしょう。
リスクを伝えたときに、どのような対応をするかによって、根本的な原因がわかることもあります。
話し合う機会を持ち、できるだけ理解できる範囲でリスクを伝えることは非常に重要なプロセスです。
地域との交流機会を増やす
地域との交流機会を増やすことも、ゴミ屋敷化を防ぐ方法の一つです。
社会からの孤立は、孤独感を深めて生きがいの低下や孤独死に繋がります。
地域との交流機会が増えることで生きがいが生まれ、ゴミを片付けようという気力が湧いてくるでしょう。
特に家族や親戚が遠方に住んでいる場合は、地域のサポートが不可欠です。
見守りサービスなど自治体のサポート制度や民生委員などの協力を得ることもできるため、無理のない範囲で地域との交流を持てるように情報収集を行ってみてください。
行政に相談する
すでにゴミ屋敷化が始まっている場合は行政に相談することで、いくつかの解決策が見つかることがあります。
- 介護サービスの利用:定期的に他人が訪問することでゴミ屋敷化を防げる
- 高齢者ごみ出し支援制度の利用:各自治体で実施されているサービスを利用できる
自治体によっては、高齢者のゴミ出しをサポートする制度が整っているため、ボランティアをお願いできることも少なくありません。
遠方に住んでいて様子を見に来ることが難しいという場合は、行政の支援制度などを活用することがおすすめです。
もし実家がゴミ屋敷になったら…解決策は?

知らない間に実家がゴミ屋敷になってしまった…そんなときはどう対処すればよいのでしょうか?
さまざまな方法がある中で、もっとも対処しやすい方法を3つご紹介しましょう。
①家族・親族で片づける
本人の意見を聞きながら片づけをしたい・協力してくれる家族や親族が多い場合は、自分たちで時間をかけて片づけることができます。
この方法のメリットは、本人の意見を尊重できること。
時間はかかりますが、体調が良く、コミュニケーションが取れる場合は、最良の方法といえるでしょう。
②行政へ相談する
各自治体では、ゴミの片づけに対する支援策が行われています。
自分たちでは手に負えない、どうしたら良いのかわからないという場合は、地域包括支援センターや市区町村の窓口へ相談してみましょう。
利用可能な制度やサポートは、自治体によって異なります。
どんな制度があるのか、事前に情報収集をしておくことがおすすめです。
③専門業者へ依頼する
費用はかかりますが、不用品の回収などの専門業者へ依頼することも検討してみてください。
ゴミ屋敷化が進んでしまっている場合、素人では太刀打ちできない状況になっていることも多いものです。
粗大ごみの回収はもちろん、害虫駆除や消臭、片付け後の清掃までお願いすることができます。
時間や労力をかけなくても、納得のいく清掃を行ってくれる業者は複数ありますので、実際に見積もりを取ってみましょう。
まとめ

高齢者のゴミ屋敷問題は、決して他人事ではありません。
原因と解決策をしっかりと理解し、万が一ゴミ屋敷問題に直面することがあったら、できるだけ早めに対処することが大切です。
特に遠方に住んでいる場合は、頻繁に連絡を取り合い、現状を常に把握できるようにしておきたいものです。