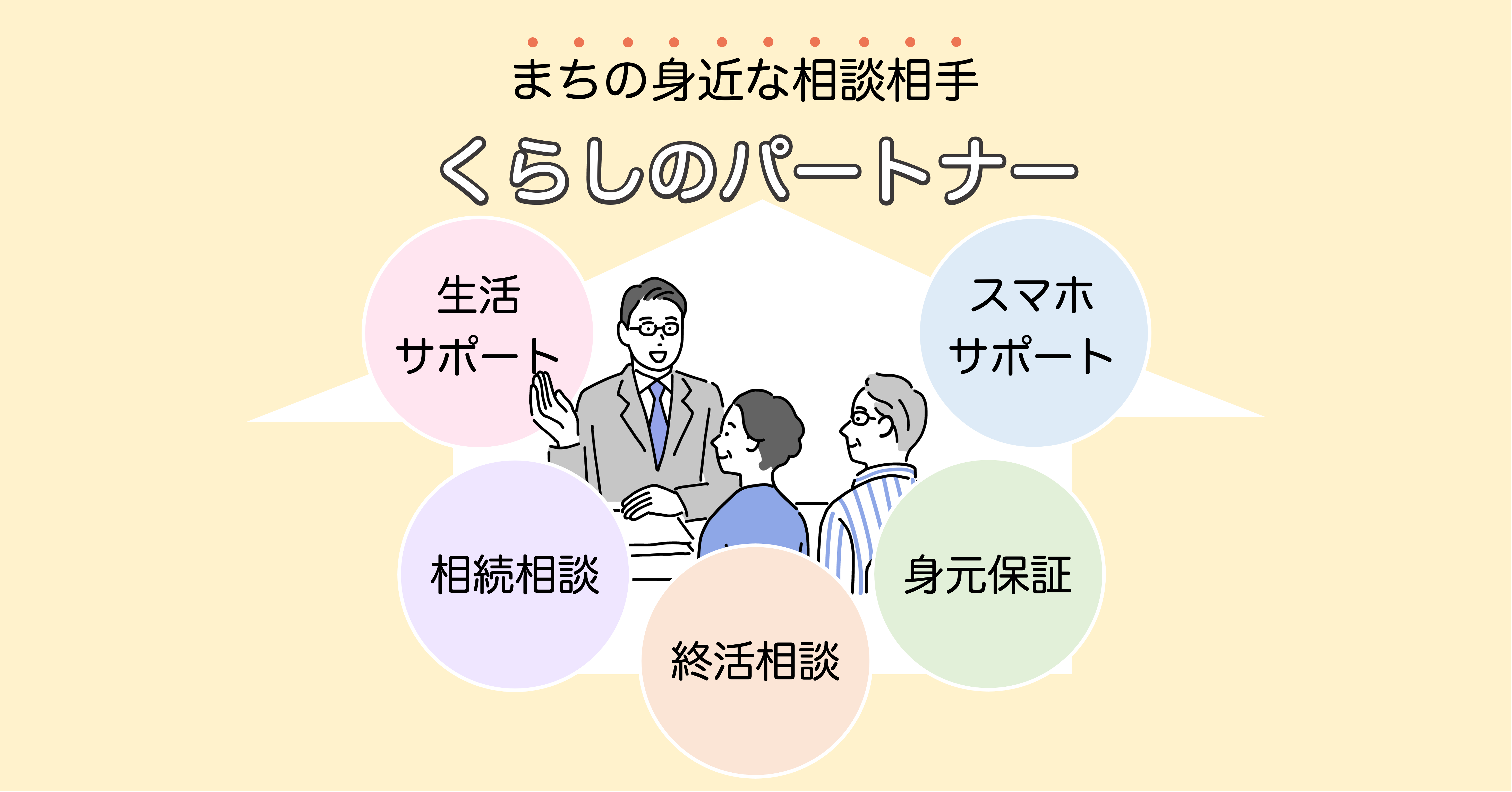日本全国には様々な病院があります。
例えば『〇〇クリニック』『◇◇医院』『△△耳鼻咽喉科』『■■病院』等がイメージできるのではないでしょうか?
小さな病院から大規模なものまで、様々な病院がありますが、それぞれには役割があり、患者の状態に合わせて受診・入院・治療が行われています。
大きな総合病院と聞いて、『入院期間が短い』ということをイメージする人も多いかもしれません。
それには理由があり、適切な医療が国民に平等に受けられるシステムのひとつなのです。
今回は、入院設備のある病院にスポットを当てて、その入院が果たす役割を説明していきます。
まずは整理!病院とクリニックの違い

『病院』と『クリニック』は、医療法によって病床数で分類されています。
具体的には、20床以上の病床を持つ医療施設が病院で、0~19床がクリニックです。
よって、医療法では入院設備のないものは『病院』とはいわず一般的には『クリニック』等で表現しなければなりません。
私たちが普通に生活するうえでは、すべての医療機関を総称して『病院』と呼んでも差し支えないでしょう。
病床の4つの種類

①一般病棟
簡単にいうと『一般病院は特定の専門領域を持たない病院』と表現できます。
一般病棟は内科や外科、整形外科など複数の診療科からなる混合病棟です。
急性期や回復期、慢性期、終末期など、さまざまな段階にある患者が入院しています。
一般病床の平均在院日数は、17日程度とされており、決して長い間入院できないことが分かります。
②療養病床
療養病棟は急性期の治療を終えて病状は安定したものの、長期にわたって療養を必要とする患者に医療と介護を提供する病棟です。
例えば・・・
■酸素吸入が常時必要な方
■重度の糖尿病の方
■IVH(在宅中心静脈栄養)の方
※在宅中心静脈栄養は、食事が口から摂れない患者さんや体力低下を防ぐ必要のある患者さんの為に有効な治療法で、 高カロリーの栄養輸液を体内の中心に近い太い静脈から継続的に入れる方法です。 通常の腕の細い血管の点滴とは違い、太い静脈からのため血管を刺激しないで苦痛なく必要な栄養分を補えます。
など慢性疾患のある患者さんが入院しています。
③回復期リハビリテーション病棟

この病床は『介護』と特に関係性が高いものになります。
回復期リハビリテーション病棟は、急性期治療を終えた患者の在宅復帰をめざす病棟なのが特徴です。
厚生労働省により、脳血管疾患や脊髄損傷、頭部外傷、脳腫瘍など、対象の疾患が定められています。
脳卒中や骨折など、突然起こる病気や怪我の他、急性期病院で手術や治療を受け、無事に状態が安定し始めると、患者さん本人もご家族安心すると思いますが、麻痺などの後遺症や退院後の生活が心配になります。
そこで、『その後の回復期をどのように過ごすか』が大切になってくるのです。
急性期病院は「命を救うこと」を大きな使命としており、症状が安定した患者には退院していただく必要があります。
そのため入院期間が短くなります。一方回復期リハビリテーション病棟は、対象となる疾患や重症度により異なりますが、最長180日という長期入院が可能となります。
機能の回復や、日常生活に必要な動作の改善に向けて、集中的にリハビリを行うことが、社会・在宅復帰後の生活をいかに不自由なく過ごせるかが重要になります。
具体的な入院期間の最長日数
【180日間】
■高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷および頭部外傷を含む多部位外傷の場合
【150日間】
■脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後、または義肢装着訓練を要する状態
【90日間】
■大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折、または2 肢以上の多発骨折の発症後、または手術後の状態
■外科手術または肺炎などの治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態
■股関節または膝関節の置換術後の状態
■急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患または手術後の状態
【60日間】
■大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋または靭帯損傷後の状態
骨折などして、一般病棟から回復期リハビリテーション病棟に転院した場合、リハビリを継続して行うことになります。
しかし、上記のように疾患によって国で定める期間が決まっており、それ以上は入院できないことになっているのです。
よって、入院と同時に「あなたの入院期間は〇月〇日までです」と伝えられます。
④地域包括ケア病棟

地域包括ケア病棟は、急性期治療を終えた患者や在宅療養中に悪化した患者の在宅復帰をめざす病棟です。
回復期リハビリテーション病棟と同じく在宅復帰をめざす病棟ですが、地域包括ケア病棟には対象の疾患がありません。
また、入院日数上限が回復期リハビリテーション病棟よりも短く、最長60日となっています。
精神科の入院について

認知症や精神的に不安定になり精神科に入院することもあると思います。
精神科の場合、上記で説明した病院の入院とは違い、少し特別な形式での対応となります。
①任意入院
患者本人の意思によって入院するものです。
症状が改善し、医師が退院可能と判断した場合や、患者さん本人が退院を希望したい場合に退院となります。
②医療保護入院
精神障害があり、医療と保護のために入院の必要があると判断された場合の入院です。
患者本人の代わりに家族等が入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。
連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要となります。
③応急入院
精神障害があり、医療と保護のために入院の必要があると判断されたとしても、その患者の家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院となります。
④措置入院
2名以上の医師(精神保健指定医)の診察により、精神障害のため自分を傷つけたり他人に危害を加えようとする可能性があると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります。
この記事で伝えたい事(まとめ)

これまで説明したように、医療に関しては『病院』で治療を受けることになりますが、病院には種類があり、そこで行われる治療等に違いがあります。また、入院することができる期間も決まっており、それを超えての入院は出来ないことになっています。
『介護』と『医療』は密接な関係にあり、介護を重視する状況か、医療を重視する状況かで病院への入退院や施設への入退所を決めなければなりません。
医療保険制度や介護保険制度はとても複雑で、一般の方にとってもなかなか難しいと思います。
そんな時は、病院や施設で常勤している『社会福祉士』に尋ねると親切に説明してくれます。