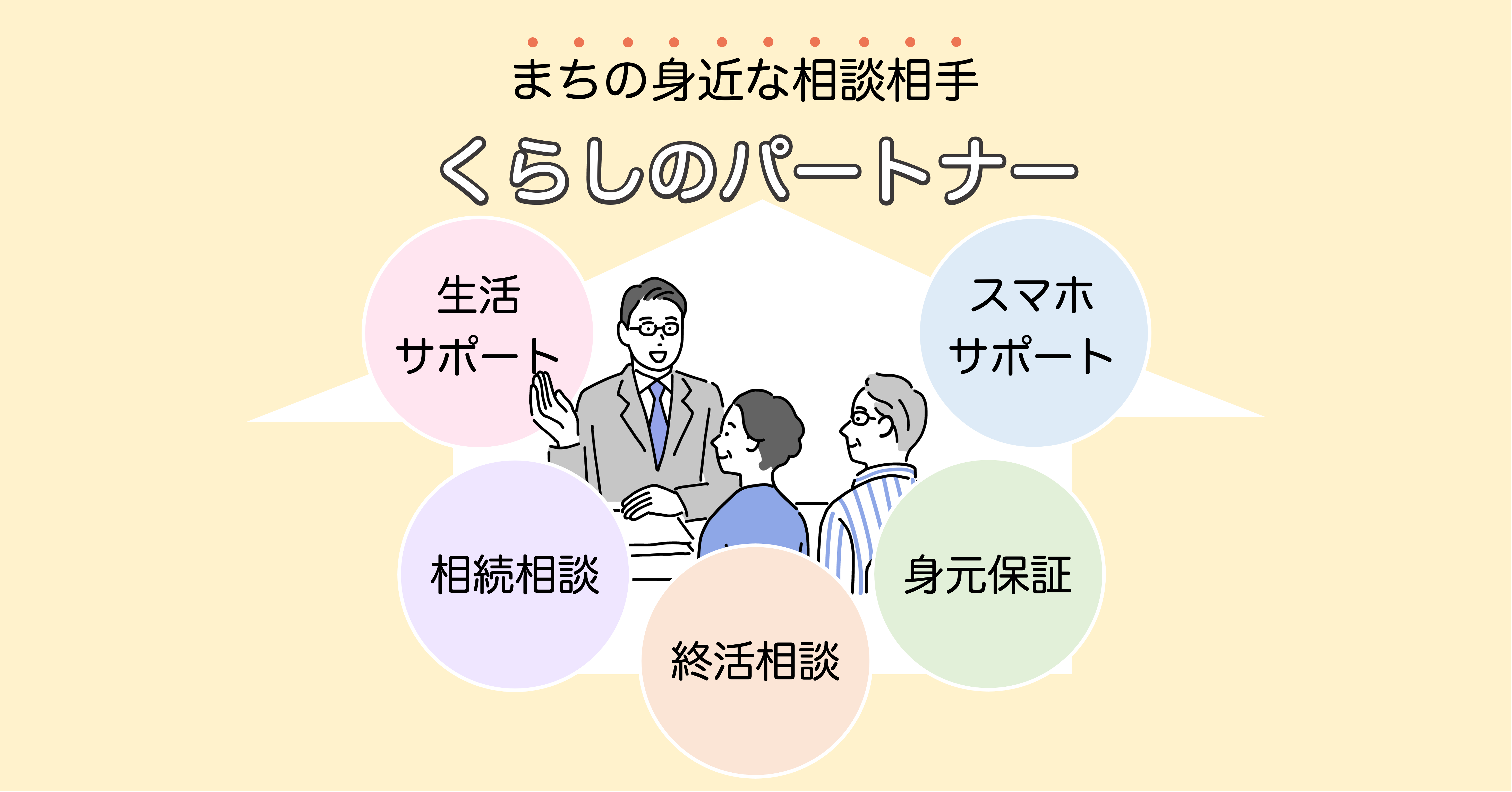俗に言う『風邪』が2025年4月より新型コロナウイルス感染症と同じ5類感染症に分類されることになります。
『風邪』は正式名称を『急性呼吸器感染症』といい、今までは医療機関への報告義務はなく、感染症法上でも分類はされていませんでした。
5類感染症といえば、パンデミックを引き起こした新型コロナウイルス感染症と同じ位置づけとなるため、「何か影響があるのではないか?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、普通の『風邪』が5類感染症に分類されることで、私たちの生活にどんな影響があるのかについて解説します。
『風邪』が5類感染症になるってどういうこと?

5類感染症と言えば、新型コロナウイルスが2類から移行したというニュースで耳にした方も多いはずです。
そもそも5類感染症とはどんな定義なのか、なぜ普通の『風邪』を5類にするのかについて解説します。
5類感染症の定義
日本で感染症は「感染症法」に基づき、危険度や社会的影響の大きさによって1類から5類に分類されています。
その中で5類感染症は、最も危険度が低いとされるグループです。
ただし、感染拡大を防ぐために適切な対応が必要な病気も含まれます。
| 特徴 | 日常生活で広がる可能性がある感染症や、予防が重要な感染症が含まれる。 |
| 危険度 | 命に関わる危険性は1〜4類より低いが、注意が必要な病気。 |
| 報告義務 | 必ずしも全ての感染症が国への届け出対象ではない。(届け出が必要なものと不要なものがある) |
現在の『風邪』の扱い
現在の日本は、俗に言う『風邪』は、感染症法上の分類には含まれていません。
つまり『風邪』という病名そのものは1類から5類のどの感染症にも該当しない状態なのです。
『風邪』は日常的に非常に多くの人がかかるため、感染症法で特定の報告義務や隔離措置は求められていないのが現状です。
ただし、風邪の原因がインフルエンザウイルスやRSウイルスなどの場合、それぞれ該当する感染症として扱われる可能性があります。
なぜ『風邪』を5類にするのか?
では、なぜ『風邪』を5類に分類することになったのでしょうか?
『風邪』を5類感染症とする理由は、感染拡大防止と社会的予防の重要性を認識し、適切な医療対応を可能にするためです。
『風邪』は日常生活で広がりやすく、重症化リスクがある人々を守るためには、基本的な予防策の徹底が欠かせません。
『風邪』を5類に位置づけることで、他の感染症との区別が容易になり、地域ごとの感染状況を把握しやすくなります。
医療資源を適切に配分し、社会全体での感染対策の効果を高めることなどが期待されているのです。
日常生活への影響はどうなる?

『風邪』が5類感染症に位置づけられることで、私たちの日常生活に影響はあるのでしょうか?
4つの項目をピックアップしてご紹介します。
検査や治療方法の変化
『風邪』が5類感染症に分類されると、原因となるウイルスを特定する検査が普及する可能性があります。
現在は『風邪』の診断にウイルスの特定検査を行うことは少ないですが、感染症として位置づけられることで、公的な検査体制が整備され、迅速な診断が可能になるかもしれません。
現在の『風邪』治療は主に症状緩和を目的とした対症療法が中心ですが、5類感染症として管理されることで、治療方法がより体系化される可能性があります。
5類感染症として分類されることで、特定の検査や治療に対して公的支援(費用補助)が検討される可能性もあり、必要な診療や薬を受けやすくなることも考えられるでしょう。
費用の変化
患者が負担する治療費に関しては、現状と大きく変わらないといわれています。
報告を求められる医療機関への負担は懸念されていますが、5類に分類されたからと言って患者の負担が増えるということは、現状ではありません。
外出や隔離ルールの変化
『風邪』が5類に分類されても、移行前の新型コロナウイルス感染症のように外出や就業が制限されたり、隔離が必要ということにはなりません。
厚生労働省では「風邪をひいても就業制限や登校制限の対象とはならない」と定めています。
ただし、感染の拡大を防ぐという意味や、回復を早めるという自主的な意志で休むことは今までと同じように考えられるでしょう。
出勤・登校ルールの変更
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時は出勤や登校ルールが変更されましたが、『風邪』が5類に分類されたことで出勤や登校が制限される可能性は低いといわれています。
インフルエンザに罹った場合は、学校保健安全法に基づいて、発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)経過するまでは登校が禁止されていますが、これは感染の拡大を防ぐための措置です。(ちなみに、インフルエンザの出席停止は欠席日数には入りませんが、『風邪』による欠席は欠席日数に含まれます。)
『風邪』について、今後会社や学校のルールの変更がある可能性はゼロではありませんが、すぐに変更されるということはないでしょう。
私たちが今できることは?

『風邪』を5類に分類する目的は、呼吸器感染症の動向を把握することや、未知の呼吸器感染症が発見された場合に感染源を探知することにあります。
私たちが今できることには、どんなことがあるのでしょうか?
正しい情報の収集
『風邪』が5類に分類されることは、私たちにとって新しい情報であり、変化の一つです。
一定の変化がある場合に注意したいのは、正しい情報を収集すること。
SNS上で拡散されている誤った情報を信じてしまったり、単なる噂話のレベルに振り回されたりすることは避けなければいけません。
政府や公的機関の発表を基本とし、わからないことがあれば医療機関などに直接相談することをお勧めします。
感染対策の継続
感染対策の継続は引き続き行いましょう。
- 手洗い・うがいの励行
- マスクの装着
- 早めの受診
- 部屋の換気
などは、『風邪』などの感染症には有効な対策です。
また、規則正しい生活や適度な運動は免疫力を高めるために推奨されています。
家庭はもちろん、学校や職場でも感染を防ぐための予防策は継続する必要があるでしょう。
自分に合った行動指針を持つ
自分に合った行動指針とは、自分の生活環境・健康状態・仕事や学校などの状況に応じて、感染症対策を実践することです。
免疫力の低下・持病の有無・高齢者や子どもとの同居などを考慮し、感染症のリスクに対する意識を高め、適切な対策を取ることが重要になります。
風邪やインフルエンザの症状が出た場合は、症状に応じた対応をし、他の人への感染拡大を防ぐことを心がけましょう。
無理に外出せず、早めに休養することが感染防止につながります。
自分や家族の体調に合わせて、不要不急の外出を控える・混雑を避けるなどの調整を行い、自分に合った方法で感染症のリスクを最小限に抑えることがポイントです。
まとめ

風邪が5類感染症に分類されても、私たちの生活に大きな影響はないと考えられます。
ただし、感染症防止における個々の行動がより重要になるでしょう。
自分に合った行動指針を持ち、生活環境や健康状態に応じて、効果的な予防策を実践することが大切です。
政府や公的機関の発表した最新の情報を収集し、柔軟に行動を調整することで、感染拡大を防ぎ、社会全体の健康を守ることができるはずです。