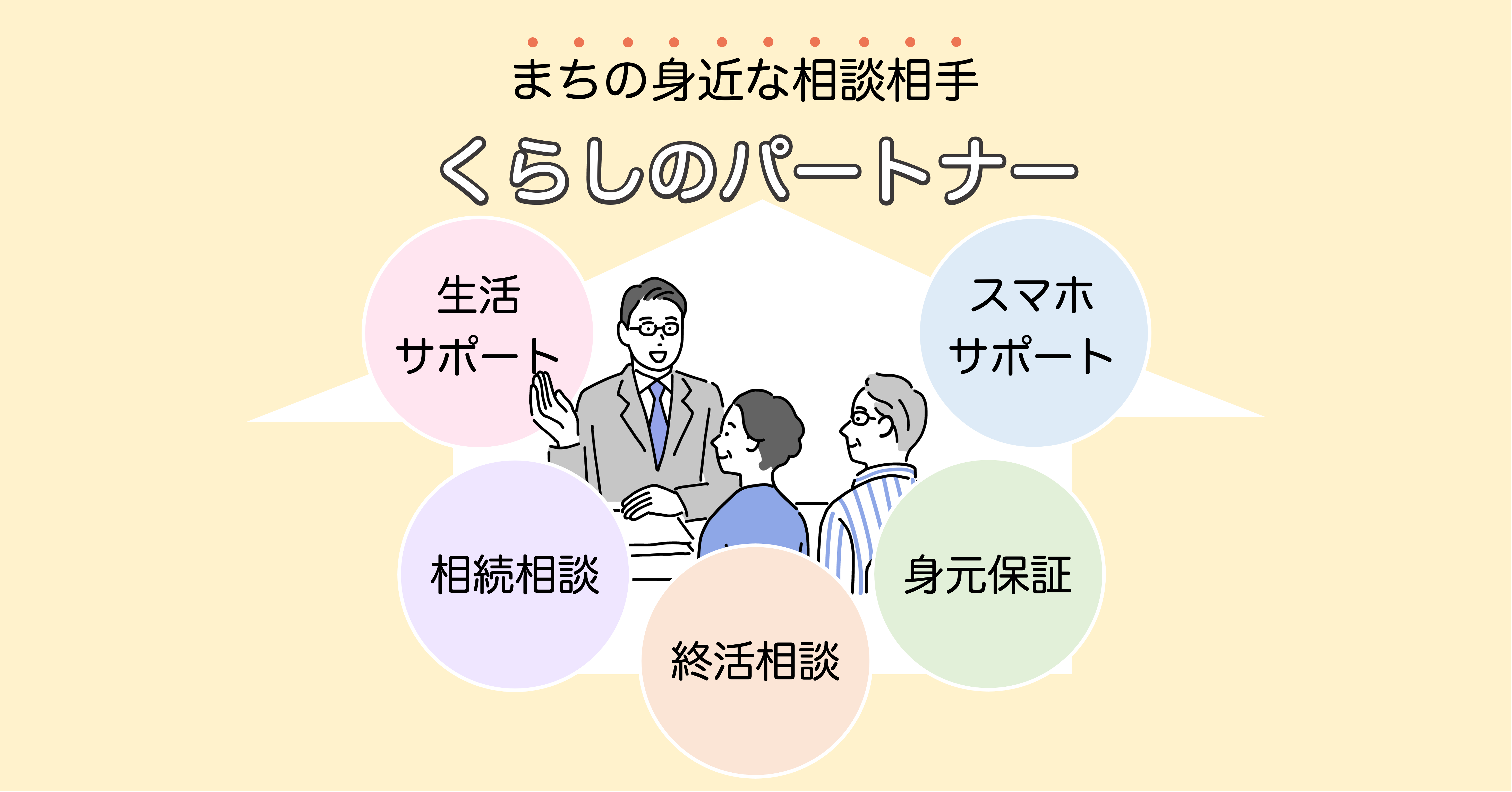地震・ゲリラ豪雨や台風による洪水…
近年の日本では、自然災害によって大きな被害を受けるケースが増加しています。
自然災害は在宅介護をしている家庭にとっては、大きな脅威の一つです。
この記事では、介護を担う家庭が被災した場合はどう対応すべきなのか、備えておくべきものは何なのかなどについて詳しくご紹介します。
いつ起きてもおかしくない自然災害に向けて、ぜひ参考にしてください。
被災した場合の対応はどうなっている?

自宅が被災して避難所などでの生活を余儀なくされた場合、今まで受けていた介護サービスはどうなるのでしょうか?
被災した高齢者の方向けに厚生労働省が通知した内容をご紹介しましょう。
避難先でも対応は可能
被災前に介護認定を受けて介護保険のサービスを受けていた方は、避難所・避難先のホテルなどでも介護サービスを受けることができます。
また他の市区町村の避難所や親族の家などへ避難されている場合も同様で、介護サービスを受けることが可能です。
デイサービスの利用などについては、施設の安全確認ができていれば利用できます。
被災により介護が必要となった方の場合は、できるだけ早めに市区町村の介護保険担当窓口へ申請を行ってください。
福祉用具の再レンタルもできる
車いす・杖・介護用ベッドなど、レンタルしていた福祉用具が無くなってしまった場合は、再レンタルすることが可能です。
ケアマネジャーやレンタル業者に連絡を取り、再レンタルの手続きを取りましょう。
また介護保険の被保険者証を紛失してしまった場合も、介護業者に氏名・住所・生年月日を伝えればサービスを受けることができます。
特例制度の活用
被災により、著しい損害を受けた場合は、特例措置が取られます。
- 介護サービスの利用者負担を支払う必要がない
- 他の市区町村へ避難しても住民票の異動をせずに介護サービスを受けることができる など
自宅とは異なる市区町村でも対応は可能です。
市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターへ相談を行うことで、特例措置が受けられる場合がありますので、介護サービスで困ったことがあればすみやかに相談しましょう。
万が一に備えて・在宅介護者が備えておくべきもの

いつ起こるかわからないのが自然災害の怖さです。
『うちの地域は大丈夫だろう』と思わずに、いつ何があっても良い対策を取っておきたいもの。
万が一に備えて、在宅介護を行っている方が備えておきたい準備についてご紹介します。
絶対に必要なものを優先して考える
準備するものの基準は、絶対に必要なものを優先して考えることです。
電気・水道が使えない、食料の確保には時間がかかるといった災害時の避難をシミュレーションしてみましょう。
十分な荷物を持って避難できることはごく稀であり、家自体が倒壊して必要なものを取り出せないこともあります。
介護者や要介護者にとって必要なものをピックアップし、準備しておくことが大切です。
絶対に必要なものとは?
絶対に必要なものとは、要介護者の生命維持に関わるものです。
- 医薬品
- 介護食
- 飲料水
などが該当します。
特に高齢者の方で嚥下機能(飲み込む力)が低下されていてとろみ食を必要とされている方の場合は、とろみ剤など、普段の食事に近くなるようなものも準備しましょう。
避難所の食事はおにぎり・パンなどがメインになります。
レトルトパックの介護食などは非常に便利ですので、最低3日分の食事が賄えるとベストです。
また慢性疾患などで薬を服用されている場合は、その薬がどういう薬なのか、途切れさせてはいけない薬なのかを介護者の人が理解しておきましょう。
被災した場合、思うように医薬品が手に入らないことがあります。
かかりつけ医や薬剤師と相談して、どのくらいの量を常備しておくべきなのかを知り、事前に準備をしておくことはとても重要です。
非常時の電源確保
人工呼吸器・吸引機・電動車いす・在宅酸素療法機器など、電気を必要とする機器を必要とされているご家庭では、停電時の対応についてしっかりと準備しなくてはいけません。
- 日頃の点検を怠らない
- 停電時の使い方・対応を確認する
- 停電時に電源が確保できる発電機などの利用を検討する
説明書には、停電時の対応が書かれているはずです。
自分ではよくわからないという方は、ケアマネジャーや医療機器の取り扱い先などに使用方法を確認をしてください。
万が一を想定したシミュレーションが大切

突然起こる自然災害…ここ数年で多くの被害が各地で報告されています。
決して対岸の火事と捉えず、万が一の事態を想定したシミュレーションをしておかなくてはいけません。
どんな事態を想定しておくべきなのか、4つのパターンをピックアップしてご紹介します。
要介護者の状態に合わせたシミュレーションを
在宅介護を受けられている要介護者の方は、それぞれ介護度が異なります。
要介護者の方の状態に合わせたシミュレーションをしましょう。
- 一人で動けるか・動けないか ⇒ 第三者の助けが必要?
- 一緒に住んでいる家族はいるか ⇒ 安否を確認する方法は?
- 避難先で生活することが可能か ⇒ 福祉避難所の利用は?
など、介護度や生活環境に応じたシミュレーションが必要です。
台風などの場合は、予報で事前に危険を予測することができます。
人工呼吸器などの医療機器を使用している場合などは、早めに緊急時の対応を準備しなくてはいけません。
介護サービスが受けられない想定を
公共交通機関が被災したり、道路が寸断されたりして、介護のスタッフが仕事に従事できないことも考えられます。
訪問介護や訪問看護、利用していたデイサービスなどが受けられない可能性も考えておきましょう。
要介護者にとって必要なケアを日頃から把握し、万が一介護サービスが受けられない場合はどのような対応が必要なのかをケアマネジャーや医師・看護師などに相談してください。
大規模な災害の場合は、一定期間介護サービスが受けられないのが現状です。
介護度の重い方や医療機器を使用されている方などは、特に対策を考えておく必要があります。
一人暮らしの場合の安否確認方法
介護を受けていなくても、高齢者の一人暮らしの場合は安否確認方法を準備しておくことが大切です。
近くに家族・親族がいる場合は、誰が助けに行くのか、何を持ち出すのかなどを本人も含めて話し合っておきましょう。
遠方ですぐに助けに行けないという場合は、近隣住民の方との連携が欠かせません。
民生委員・自治会長など、頼りになる存在の人に状況を知っておいてもらう必要があります。
介護を受けている方の場合はケアマネジャーに緊急時の対応を確認し、自宅とは別に避難する際の準備をしておきましょう。
大切なのはライフライン停止の対応
自然災害でもっとも大きな被害となるのは、ライフラインのストップです。
電気・ガス・水道…介護を受けている方にとっては、どれも非常に大切な要素になります。
特に停電と断水には十分な対策が必要です。
医療機器で電源が欠かせない場合は、発電機やバッテリーを準備したり、日頃から飲用水を確保しておくなど対応を行いましょう。
災害時は介護サービスもストップすることを知っておこう

災害はいつ起こるかわかりません。
在宅介護をされているご家庭にとっては、十分な準備や確認が必要です。
避難先でも介護サービスを受けることは可能ですが、甚大な被害を受けた地域では介護サービス自体がストップしてしまうことも考えられます。
停電や断水が起きた場合のことも考えて、ケアマネジャー・医師・看護師などに事前に相談をしておきましょう。